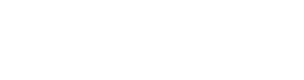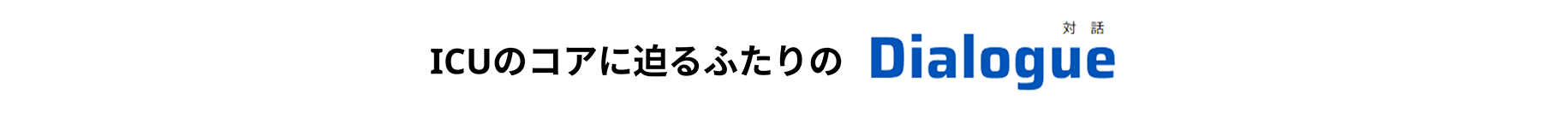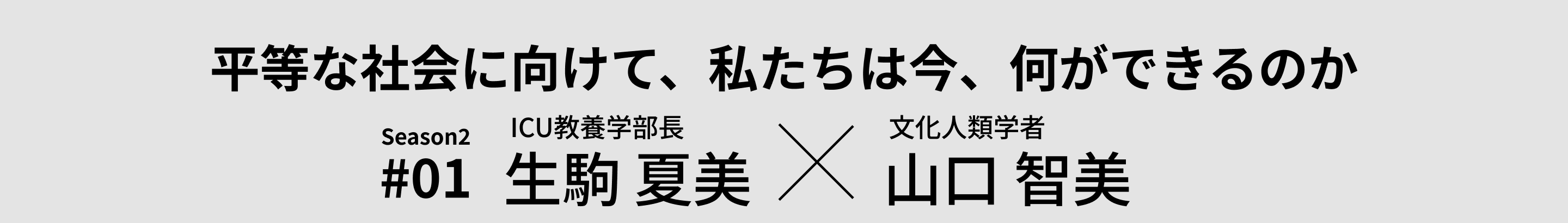
#人権 #文学 #ジェンダー #米国 #新政権
このDialogueは2024年11月8日に行われた。
文学とジェンダーを専門とする生駒夏美ICU教養学部長と
文化人類学者として米モンタナ州立大学で
長年教鞭を執ってきた山口智美氏(現・立命館大学教授)。
ジェンダー研究を共通項とする二人が語る、人権へのミッションと実践。
誰もが活躍できる世界の構築に向けて
平和に資する「人」を育てる
1953年、ICUで最初の入学式に出席した新入生は、それぞれが「世界人権宣言」の原則にたち、大学生活を送る旨を記した誓約書に署名をした。基本的人権尊重を原則とする「世界人権宣言」である。慣例として今もなお、ICUではすべての学生が入学式で「世界人権宣言」の原則を遵守することを記した学生宣誓書に署名している。「世界にむかって開かれた国に日本を革新し、人類平和のために貢献することのできる、国際的社会人の育成」―そのミッションは70年を超えて、「人権」を基盤とするICUコミュニティの「living & learning」の全てにおいて実践されている。
ICUのリベラルアーツ教育において、国際的社会人育成の根幹をなすのは対話(dialogue)を通した他者理解である。対話を通して違いを乗り越え、他者性をもった人とともに協働できる能力を育むのだ。では、日々のキャンパスライフにおいて乗り越えるべき違いとはなんだろう、という問いが生まれる。生駒学部長は、「世界的にこれまで乗り越えるべき違いは人種や宗教だったが、90年頃からジェンダーも重要な課題となっている」と指摘する。
日米のジェンダーの課題と今後、そしてジェンダーを内包する大きな概念であるDEI(Diversity, Equity, Inclusion)の理想と可能性とは。
Paragraph 01
ジェンダーの現状と日米の大学の取り組み
――「ジェンダー」という言葉は、今でこそ当たり前に使われているが、歴史を紐解くと、厳しいアンチジェンダーの時代があった。生駒学部長と山口教授に、その当時の状況から振り返っていただいた。
生駒学部長 私がICUに赴任した2003年は、とても激しいアンチジェンダーの時代でした。「ジェンダー研究なんて正当な学問ではない」と言う人や、「ジェンダー研究は女性のための学問」と言う人もいました。あからさまに反発する学生もいて、最初の5年間ほどはとてもアウエーな感じでした。幸いなことに、ICUの教員からの大きな反発はなく、むしろぶれずに支えてもらえましたが―。
山口教授 1999年に「男女共同参画基本法」が施行されその後、バックラッシュと言われるジェンダーに対する反発の時代が始まりました。2002年から2005年ぐらいまでが最も激しかった時代で、生駒学部長がICUに着任した時期は、その真っただ中と言えます。

生駒学部長 他大学でもジェンダー研究を行っている教員がいましたが、その人数は多くはなく、孤立している状況でした。ICUは先進的な取り組みをしているという自負もあり、そうした教員のネットワーキング化など、様々な活動をしていました。
――ICUはジェンダー研究では日本における草分け的な存在。研究対象にするだけではなく、キャンパスの「living & learning」の全てにおいて、世界基準での実践を目指している。ジェンダー研究に対する逆風が吹く中で、2004年にオープンしたのがジェンダー研究センター(通称CGS:Center for Gender Studies)※1。生駒学部長も設置準備から運営に関わった。学生にも開かれた場である同センターは当時としては国内では先駆的な取り組みであり、先行事例として多くの大学がICUの知見を共有することになる。
生駒学部長 CGS(ジェンダー研究センター)の前身は、私が着任する前から社会学の教員が行っていた性的マイノリティ(現在ではLGBTQ※2と称されることが多い)学生の支援活動でした。ある学生が希望した学籍簿の名前の変更について、その可否を文部科学省に確認して、実際に名前変更を行えるようにしたという実績が一つの契機となって、ジェンダーに関する研究や教育を積極的に進め、マイノリティ学生を支援するための組織としてCGSができたのです。CGSが開設した翌年には、学部教育の一環として「ジェンダー・セクシュアリティ研究」が立ち上がり、現在も教養学部が擁する31メジャー(専修分野)の一つとして続いています。
山口教授 トランスジェンダーの学生の名前変更ということでは、アメリカでは政権によって扱いが変わってきました。オバマ政権の時代に教育省が「タイトルⅨ」と呼ばれる教育における性差別を禁止する法律に関する指針を出し、ジェンダーアイデンティティに基づく差別的取り扱いを禁止しました。そして指針に基づき、大学でも学生が望めば名前を変えられることが定められたのです。でもそれは第一次トランプ政権で反故になりました。バイデン政権になって元に戻ったのですが、今度は第二次トランプ政権となるので、また叶わなくなりそうです。名前の変更に限らず、アメリカではジェンダーに関する指針は政権が変わるとコロコロ変わります※3。
――さらに広く、アメリカの大学のジェンダーに対する取り組みはどうなのだろうか。
山口教授 私が所属していたモンタナ州立大学は、人類学など人文・社会科学系の専門もありますが、それ以上に工学やコンピュータサイエンス、化学などのいわゆる「STEM(Science、Technology、Engineering、Mathematics)」に力を入れている大学でした。その中で、学際的プログラムとして「女性学ジェンダー・セクシュアリティ研究」を担当していました。メジャー(主専攻)としたかったのですが、STEMに力を入れている大学ということもあり、保守的な州ということもあって、マイナー(副専攻)にしかできず、クラスもとても少なかったですね。
もちろん、アメリカには歴史のあるジェンダー研究プログラムのある大学はたくさんあります。私の学んだミシガン大学は、1970年代から学生のイニシアチブで研究が始まっており、ジェンダー研究所も、またLGBTQの学生たちのためのセンターもあります。そうした大学も数多くありますが、すべてがそういうわけにはいきません。州立大学は州から多くの予算がでているので、連邦のみならず州の政治状況に大きく左右され、州によって事情が異なります。私立大学も企業の寄付などが絡みますし、連邦政府の方針の影響もあり、複雑な状況です。
――アメリカでの事例を踏まえた上で、ICUの取り組みは山口教授にどう映っているのだろうか。
山口教授 ICUのCGSについて外から見ていて感じるのは、いわゆる「男女」のジェンダーだけではなく、多様なジェンダーやセクシュアリティを扱っている歴史があり、日本では先駆的な取り組みだということです。現在、LGBTQの学生が安心して学べる場はそれほど多くありません。完璧ではないかもしれませんが、安心して学べる場を作ろうという動きがある中で、大学生生活を送れるのは大変重要なことです。日本のジェンダー研究の歴史の中で、とても重要な役割を果たしてきたと思います。
生駒学部長 学生の居場所作りはCGS設立当初から一つの目的です。ICUにはCGS以外に6研究所・センターがありますが、基本的にそれらは教員の研究のための組織で、学生にオープンになっていません。一方CGSは設立当初から、学生がソファーでくつろいだり、ジェンダー研究関連の図書を借りにこられる図書室を併設するなど、学生の居場所を大事にしています。
※1…CGS:ジェンダー・セクシュアリティの研究に関心がある人たち全てに開かれた新しいコミュニケーションスペース。主要目標は① 欧米からの情報を消費する受動的な態度から脱し、世界に向けて積極的に日本の情報を発信。②アジアにおいて、女性学・男性学・ジェンダー研究に関心のある人たちとのネットワークの構築。③社会科学や人文科学だけでなく、自然科学をも取りいれたジェンダー研究の地平を切り開くため、ICUの「ジェンダー・セクシュアリティ研究メジャー」の支援。
※2…LGBTQ:レズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシュアル(Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender)、クィア(Queer)またはクエスチョニング(Questioning)の頭文字をとった、性的マイノリティを表す総称 。
※3…2025年1月20日、トランプ大統領が就任するやいなや、政府が認める性別は男と女二つという大統領令を出し、1月31日には教育省が指針を出し、バイデン政権でのトランスジェンダーの人権擁護の指針を撤廃した。
Paragraph 02
ジェンダー平等問題の一般化から高まる人権への意識
――逆風が吹いた2005年以降、日本において「ジェンダー」が使いづらい状況がしばらく続いた。だが、その後、「ジェンダー」はポピュラーな言葉として社会に定着していく。そこには、若者の意識の変化があったようだ。そのきっかけの一つが、性犯罪被害をSNSで発信する際に、ハッシュタグ「MeToo」をつけて展開した「#MeToo movement(運動)」※4だと言う。
生駒学部長 大規模な性被害が起きていることが明るみに出た「#MeToo movement」くらいから、ジェンダー問題は社会で共感を得るものになっていったと思います。日本でも、女性が「今まで我慢してきたものは性被害や性差別だったのでは」と問い始めました。今まで「ジェンダー」という言葉を毛嫌いしていた人たち、特に女性たちも、この頃から自分事として考えるようになったのだと思います。

山口教授 アメリカでも、若い世代のジェンダーに対する意識は、大きく変わってきています。例えば、2015年、連邦最高裁の判決により、同性婚が米国全土で実質的に合法化され、「同性婚は普通にあること」という意識に瞬くまに変わったのは大きいし、数年前の学生は、中学生や高校生の頃にフロリダの乱射事件を受けて、銃反対デモしていた世代でした。さらに、「#MeToo movement」や黒人に対する人種差別や暴力に抗議する「BlackLivesMatter」も起こっています。最近はとにかくインフレが激しいので、少なくともみんなが安全に手頃な価格で住める環境を作ろうという運動を学生たちが行っていることもあります。そうした若者は、ジェンダーがとても大きな問題だということを分かっているようです。特に女子学生にとっては、人工中絶を権利として認めた「ロー対ウエイド判決」が2022年に覆されたことも大きい。こうした様々な政治的危機感を持つ学生は、女性学など関連した分野を専攻する傾向が強まっています。
――では、今の日本の学生の意識に変化はあるのだろうか。
生駒学部長 ICUでもジェンダーについて問題意識を持って入学してくる学生が増えました。CGSの活動もあり、ICUはジェンダー教育に力を入れており、LGBTQ支援をしているとの評価を受けていることもあって、それを最初から知って入学する学生も結構います。そういう意味では人権意識の高い学生が増えてきていると感じます。ICUの1学年の入学定員は620人で31メジャーありますが、シングル、ダブル、メジャー・マイナーとメジャー選択の方法は複数ありますが、ジェンダー・セクシュアリティ研究メジャーを選択する学生はだいたい40人くらい。さらに近年は、ウクライナの戦争など、世界のいろいろな場所で戦争が起き、人権侵害が非常に過酷になっていることを認識する学生が多くなってきています。人権の問題が、ただ単に紙の上での理想ではなく、今現在の現実世界のことであり、自分の日常の問題でもあるという意識を持つ学生が増えていると思います。
※4…#MeToo :セクハラや性的暴行などの性犯罪被害の体験を告白・共有する際にSNSで使用されるハッシュタグ(出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/MeToo)
Paragraph 03
ICUのジェンダー問題に対する具体的取り組みと評価
――すべての学生が快適なキャンパスライフを送るための課題とは?「living & learning」の「living」の視点で大学はどのような取り組みができるのだろうか。性的マイノリティであるLGBTQの学生にフォーカスすると環境面の充実が欠かせない。他大学のモデルケースとなるICUの先進的な取り組み事例としては、学生寮とオールジェンダートイレの設置が挙げられる。
生駒学部長 もともとICUには、ジェンダー問題に関心のある学生が多くいます。CGSの設立当初はLGBTQの学生たちが活発に活動していて、キャンパスに対する要望書をまとめていました。例えば体育館やシャワー室の利用、健康診断などが男女別で困るとか、学生寮が男子寮と女子寮に分かれているのは困るなど、日常の困りごとに関する様々な要望をCGSが窓口として大学側に届けていました。その成果の一つが新学生寮です。大学側が学生たちの要望を丁寧に聞き取り、その結果、新しい学生寮ができるときに、男子と女子に加えジェンダーレスのフロアが設けられました。
――学生の思いを行政が叶える形で設置された新学生寮に対し、オールジェンダートイレは大学側からの提案で設置が進んだという。

生駒学部長 メインの教室棟にあたる本館には、オールジェンダートイレを設置しています。これはCGSからの要望ではなく、大学事務部門(施設担当)からの積極的な提案によって実現したものです。学内にジェンダー問題への理解が浸透していることが感じられた、とてもうれしい出来事でした。オールジェンダートイレは、犯罪を増やすとか女性のスペースをなくすといった誤解に基づく論調が世間に広がり、設置をひるむ傾向がありますが、ICUではデザインを工夫して、行き止まりをなくしたり、とびらの上下の隙間をなくして個室感や安心感を高める工夫をしています。安心感があり、オールジェンダーと言われなければ気づかないくらい、誰でも違和感なく使えるものにしています。
山口教授 オールジェンダートイレの設置は本当に重要な取り組みで、それがあるかないかで学生の安心感が違います。安全なことが分かれば勉強に集中できますし、キャンパスライフも楽しめると思います。アメリカの場合、学生寮については、男性と女性が同じフロアであることも多いですね。トイレに関しては日本と同様に政治イッシュー化していますが、大学では主に予算の関係から、オールジェンダートイレは不足している状況です。ジムのロッカールームも男女が分かれているケースが多いのに新設や改装が進んでいません。資金のない大学は厳しい状況ですし、そのための予算が優先的に配分されないというのも問題です。私がいたモンタナ州立大には、オールジェンダートイレは少しありましたが、潤沢に予算がある大学ではなかったこともあり、全然足りていませんでした。
Paragraph 04
ジェンダー平等の課題とジェンダー研究におけるICUにかかる期待
――行政が積極的に推進する「男女共同参画社会」は果たしてジェンダー不平等を解決できるのか。一見、ジェンダー不平等は緩和の方向に向かっているように見えるが、実際には自治体レベルで温度差があるという。
生駒学部長 「共同参画」といっても女性の労働市場への参入ばかり取り上げられていることが問題です。経済的な必然性もあって女性はどんどん労働市場に出ていくのに、古いジェンダー規範はまだまだそのままです。結局、女性は外で働き、家事も担う、子供も産めと言われるという中で、過大なプレッシャーを受けています。そうした状況でジェンダーの問題を自分事として感じる女性が増えてきて、自ら不満の声を上げ始めているのだと思います。

山口教授 男女共同参画について楽観視はできないと思います。本来なら性差別の撤廃や人権という言葉を使ってほしいのですが、男女共同参画という曖昧な言葉になり、その後バックラッシュが起きて取り組みが弱体化しました。女性活躍推進法ができましたが、それも十分に機能しているとは言えません。本来、女性差別やジェンダー差別撤廃あるいはジェンダー平等推進だったはずのものが、ずらされてしまっているのが現状です。ソーシャルメディアなどを通して、市民から様々な声があがってきますが、選択的夫婦別姓の実現や同性婚法制化など、現実的な制度転換につながっていません。アメリカも第二次トランプ政権になると、どうなっていくのか、注目しています。
――アカデミアが生み出す知見を社会に還元することで、社会全体がそこから学び、進化して、日本全体がジェンダー平等に向かう未来に向けて、日本の小さな大学も積極的に社会に関わることが期待されている。
生駒学部長 ジェンダー問題を自分事として考える声を、大学の中で研究するだけではなく、社会に向かってリーチアウトしていかなければなりません。自治体などとも協力しながら、進めていきたいと考えています。
山口教授 ICUは本当に重要な取り組みを行っています。日本のリーダーとしてだけではなく、世界にも発信していってほしいとですね。以前、ICUの学生の要望書を見る機会があったのですが、アメリカの学生にも参考になるレベルで、アメリカと日本で連帯して取り組んでいく可能性を感じました。トイレを作るというのも含めて、トップダウンではなく、スタッフの提案から始まるのも大変重要なことだと思います。世界的にジェンダー研究がバッシングを受けている時代です。トランスジェンダーに関して今後ますます批判が強まる可能性が高い中で、ジェンダー研究が何とか踏みとどまって、きちんとした方向に向かってほしい。小さな日本の中の小さな大学かもしれませんが、着実に取り組みを続け、社会に向けても発信していくことが重要だと思います。
Paragraph 05
ジェンダー問題からさらに大きな人権の概念であるDEIへ
――「人権」問題へのさらなる挑戦として、ジェンダー問題をも内包するDEI(Diversity、Equity、Inclusion)※5の実践が挙げられる。あらゆる違いをのりこえ、人権を尊重するICU。ジェンダーの先を見据えるのは、組織的にDEIに取り組み、さらに人権に配慮した社会の構築である。DEIは企業が先行して取り入れている概念だが、その実効性は現時点で未知数。そうした現実を踏まえて、DEIとどのように向き合っていくのか。
生駒学部長 DEIを取り入れる企業が多くありますが、経済的な効率や資本主義の中でしか捉えられていないのでは限界があり、人権問題という視点が欠けていると、本質的な理念はまったく捉えられないと思います。
大学として取り組む以上は、理念を重視する人権問題として取り組んでいきたいですね。特にDEIのEquityについて。平等を意味するイクオリティと公正を意味するエクイティは微妙に違うわけで、個別の背景や事情に応じた支援を行うエクイティを目指すことが大事だと思います。ICUではそういうDEIを実現していきたいと思います。
山口教授 全く同感です。理念として本質的に進めていくと同時に、現実のところでも、例えば教育の現場も教員が特定の人種なり特定のジェンダーの人ばかりがたくさんいるという環境では駄目なので、多様な環境を作っていく。ただ雇用するだけではなく、その人たちが働きやすい、働き続けたいと思う環境をどうやって作るのか。それは教員だけではなく、スタッフや学生もみんな同じだと思います。マイノリティの方も含め多様な学生や教員、スタッフを集めて、ぜひDEIを進めてほしいと思います。
生駒学部長 多様な学生が学びやすいように、心地よくサポートされていると感じられるような環境を整えるためには、教職員も多様でないといけないし、そういう多様性を受けいれるための心構えを持っていないといけない。加えて知識も必要です。特にマイノリティに関する知識を教職員がきちんと持ってないといけないと思っており、そのためのDEIだと思うのですね。本当に学生のためのDEIを推進していくことによって、結果的に社会に対してのロールモデルになっていくことが必要だと思います。本質的なDEIの実現に向けて、CGSやオールジェンダートイレなどと同じように、私達は自負を待って、日本の中で社会を引っ張っていく存在でなければいけないと思っています。
――不確実な時代にDEIが実現する未来はあるのか。

生駒学部長 これまで学内でのジェンダー問題解決をけん引してきたCGSは、ジェンダーだけではなく人種的なダイバーシティの必要性や、アクセシビリティの面で困難を持っている学生に対するサービスなどにも関わってきましたが、研究所であって事務組織ではないので、大学組織全体に与える影響力には限界があります。また差別はジェンダーだけではなく、経済格差や人種、宗教、健康など、いろいろな要素があるので、大学には、DEIを実現するための組織を設置して取り組んでいくよう、働きかけているところです。
山口教授 アメリカの今の政治状況からすると、DEIはどんどんなくなっていく運命だとは思います。今や多くのレッドステート※6では禁止になってしまいました。企業や大学でDEI部門が廃止され、DEIの取り組みを禁止する州も増えてきました。モンタナもいつそうなってもおかしくありません。そうなってしまうと、日本への影響が怖いと思いますね※7。
――DEIにおいても社会のロールモデルになるために。
山口教授 素晴らしい取り組みを進めるICUですが、東京郊外という立地条件もあり、すこし孤立しているところがあると思います。そこから脱却するためには、地域市民との繋がりが必要であり、それがないと、せっかく良い取り組みを行っていても内輪で終わってしまいます。その面では、州立大学のミッションとして地元貢献を大きく位置づけて実践していたモンタナ州立大がICUより強いところかもしれません。ICUもジェンダー平等そしてDEIに関するロールモデルになるために、コミュニティに呼びかけ提案できるようになってほしいですね。
生駒学部長 ぜひ地域のコミュニティやグローバルなコミュニティにもっと開かれた大学にしていきたいと思います。現在大学が取り組んでいる自治体との連携もコミュニティともっと関わっていきたいという考えの表れです。コロナ禍で取り組みが幾分停滞してしまったので、今また一歩ずつ、再構築しようと進めているところです。
※5…DEI:個人の多様性(Diversity)を認め、差別や過小評価を受けてきた人やグループの公平性(Equity)を担保し、多様な背景を持つ人々を受け入れる包括性(Inclusion)を重視するという人権的概念。
※6…レッドステート:アメリカ合衆国の州の近年(特に2000年以降)の大統領選挙における政党支持傾向を示す概念である。共和党を支持する傾向がある州を赤い州(red state)、民主党を支持する傾向がある州を青い州(blue state)と呼ぶ。(出典:Wikiペディア:赤い州・青い州)
※7…今年1月、トランプ大統領が就任するや否や、連邦政府や米軍でD E Iを廃止する大統領令を出し、教育省が大学に出していたDEI関連の連邦助成金をカットするなど、DEI禁止の動きが活発化。DEIをめぐる米国での状況は著しく悪化している。
【対談を終えて】
今回の対話から浮かび上がってくるICUのリベラルアーツ教育の本質とは、日常のキャンパスライフ、「living & learning」の中で自由闊達なダイアログが自然に生まれ、相互に共有されて全体に反映されていくことにあるのだろう。ジェンダー問題、DEI、ひいては人権といったイッシューさえも、ここでは改まった形ではなく自分ごととして語られ、リベラルアーツ的視点を育みつつ自由な学びの時間に繋がっている。そしてその学びは、リベラルアーツが本来目指す、人と人がよりよく生きられる社会の実現に繋がっていく。 地域から日本、そして世界へ。平和に資する人を育てることをミッションとして献学されたICU。人権問題に教育・研究の視点から取り組み、誰もが平等に活躍できる世界の構築への期待がかかる。
対談の余談
ICUの思い出
――人権意識が芽生えた入学式
- 山口教授
- ICUの入学式で世界人権新宣言を守ると宣誓したことを未だに覚えてます。入学式で行うということは、「人権を守ることをとても大事にする大学に入学したんだな」との思いを強くしたことは忘れられません。
- 生駒学部長
- 第二次世界大戦の反省から献学されたICUは、そのような悲惨な戦争を二度と起こすことがないよう、対話を通して乗り越えていこうという決意から、世界人権宣言を遵守する宣誓を開学時から続けているのです。
――人類学者への扉を開いたリベラルアーツでの学び
- 山口教授
- 在学中に平和研究の授業でアメリカ軍の横田基地に行ったことをとてもよく覚えています。基地反対運動をしている方のお話を伺ったことがとても大変印象深く、未だに覚えています。実際に基地から大きな影響を受けて市民運動をしている方に直接話を聞くことができたのは、とても貴重な機会だったと記憶しています。
- 生駒学部長
- 国内には当時から平和研究を専門として置いている大学はほとんどありませんでした。山口先生の今やってらっしゃるお仕事に、とても深く結びついているようですね。
- 山口教授
- そうですね、私は社会運動について研究しているので、実際に関わっている人に直接お話を聞いたのは一つの契機になったのかもしれません。その当時はジェンダーを体系だって学べるカリキュラムはありませんでしたが、私の卒論のテーマはジェンダーでした。現在のICUのジェンダーに対する教育・研究体制はとても素晴らしいと思います。
PROFILE
生駒 夏美
国際基督教大学 教養学部長
国際基督教大学教養学部長。2002年ダラム大学博士号(Ph.D.)取得。国際基督教大学ジェンダー研究センター長、同文学研究デパートメント長を歴任。専門分野はジェンダー、ヨーロッパ文学、文学一般、日本文学、思想史。2022年4月より現職。現在、東京都武蔵野市男女平等推進審議会委員も務める。
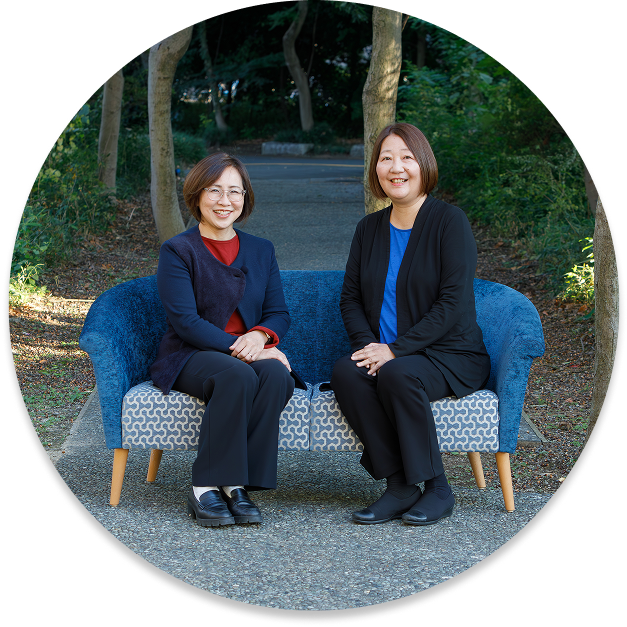
山口 智美
文化人類学学者
立命館大学国際関係学部教授。モンタナ州立大学名誉准教授(人類学)。2004年ミシガン大学人類学部で博士号(Ph.D.)取得。シカゴ大学東アジア研究センターのポストドクトラル研究員を経て、モンタナ州立大学社会学・人類学部に着任、17年間教鞭をとり、うち6年間は女性学・ジェンダー・セクシュアリティ研究プログラムのディレクターも勤めた。専門分野は文化人類学、フェミニズム、日本研究。2024年9月より現職。国際基督教大学教養学部卒業生でもある。