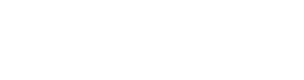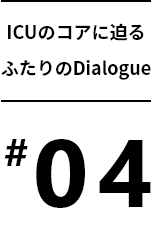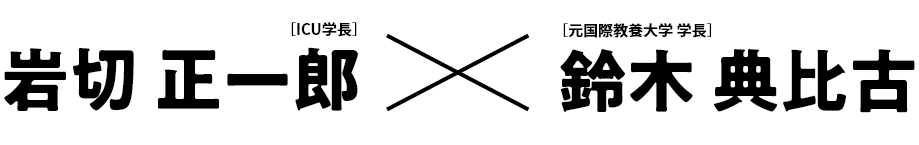秋田県にある国際教養大学(AIU)の第2代学長を2020年度まで務め、
その前にはICUで第11代学長として大学運営に心血を注いだ鈴木典比古氏。
元学長を迎えたのは、現学長 岩切正一郎。繰り広げられた対話の記録。
#世界通用性 #リビング&ラーニング #複数言語主義 #common good
「国際性」と「リベラルアーツ」から考える
大学の「世界通用性」とは――
「国際」と名の付く大学は日本に多数存在するが、何をもって「国際」なのかは釈然としない。
さらに、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響によって、「グローバル」や「国際性」のあり方が変わりつつある。
そうした中、改めて「国際性」とは何なのか、「世界に通用する」とはどういうことなのか、対話を通して考えを巡らせる行為が必要ではないだろうか。
ともに大学名に「国際」を冠し、単一学部によるリベラルアーツ教育を実践するICUとAIU。両大学で舵取りを務めた鈴木典比古氏と、現在まさにICUを牽引する岩切学長の対話を通して、そのDNAを解き明かしつつ、日本の大学の「世界通用性」について考える。
Paragraph 01
「国際」の意味づけの変容と
オンライン化がもたらした変化。
大学における「国際性」とは何か。海外大学との学術交流が活発である、派遣・受入留学生の数が多い、卒業生が国際機関や外資系企業で活躍している……尺度は多様であり一口で言い表すことは困難だろう。「国際」という言葉が持つ意味も時代の流れとともに変わっており、岩切学長は次のように語る。「私がICUに着任した四半世紀前は、『国際』あるいは『インターナショナル』という言葉が主流だったように思いますが、いつしか『グローバル』という表現に置き換わってきたような気がします」。
今、世界で起きている問題に目を向けても、国家間の問題というよりも、グローバル・イシューに行き着くことが多い。「人間社会の構造自体がグローバルなものになっている」と岩切学長。「格差社会を例にとっても、国家間で解決できる問題ではなく、世界の中で富める者と貧しき者が存在している。こうした『グローバルな構造』をしっかりと意識することが重要です」。
「国際」の意味づけの変容とともに、国際的な教育の形態にも変化が生じている。大きな要因としてインターネットの発展が挙げられるが、昨今の新型コロナ禍が授業のオンライン化を急速に後押ししたことは言うまでもないだろう。オンライン授業の進展による変化について、鈴木氏は次のように語る。「これまでは留学などで『人』が世界を行き来していたのが、今では『授業』がネットワークを介して地球上をぐるぐると回っている。閉ざされた空間で行われた授業が突然世界に開かれたことで、教員一人ひとりの教育力が浮き彫りにされ、また自らの専門性を明確にすることが求められるようになったのです」。

岩切学長もこう反応する。「その点は真剣に考えなくてはならない問題ですね。どこにいても世界中の大学の授業を受けられるようになると、『大学に足を運ばなくてもよいのではないか』と考える人も出てくる。そうなると、今後どういう形で自分たちの大学を作っていくのか、ビジョンをはっきりさせなければなりません。このことはあまり触れられていない、意外と大きな変化かもしれませんね」
5Gの到来によって今後ますます加速するであろうオンライン化。どこでもネットワークで容易につながることができる環境の中で、「国際性=国境を超えたリアルな人的交流」という時代ではなくなってきた。こうした時代において求められる国際的な学びとはどのようなものだろうか。
Paragraph 02
ICUとAIU、それぞれが目指す
世界基準のリベラルアーツとは。
「国際」の意味が変容する中でも、「国際」を大学の根幹として重視し続けるICUとAIU。そして両大学の、もう一つの大きな共通項がリベラルアーツ教育である。
ICUは、メジャー制を導入している。入学時ではなく2年の終わりまでに、31のメジャー(専修分野)から自身のメジャーを決める。人文科学や社会科学分野に加え、「生物学」「物理学」「化学」「数学」「情報科学」といった自然科学系まで文理を超えてバランスよく専門が配置されている。一方、AIUでは2021年度から、従来の社会科学系分野に加え、人文科学とともに自然科学やAIなどの最先端技術を学ぶ「グローバル・コネクティビティ領域」を開設した。鈴木氏は「これは文系と理系を完全に統合しようという試みですが、私の考えの根底にあったのはICUが持つ学問領域のバランスでした」。
「文系理系」という日本独自の従来の区分けが疑問視される中、文理の垣根を取り払った学びの体系こそが、これからの世界に通用する、世界基準の教育と言えるのかもしれない。
鈴木氏はこう続ける。「古代ギリシャ・ローマの時代、都市国家の青年教育の中で重視されたのは、体育と音楽。そして、後に導入され、重視されたのは数学でした。数学の持つ美しさや神秘さはリベラルアーツの出発点の1つになっているのだと思います」。
「ICUのコアに迫るふたりのDialogue #01」での平田オリザ氏と岩切学長の対談では、平田氏がICUに入学した当時の学長が「ICUでは虚学を教える」と宣言していた、という話が挙がった。そこでは演劇や文学、芸術といった分野がクローズアップされたが、実用性から少し距離を置いた純粋数学もまた、ある意味で「虚学」といえるだろう。

「虚学」も含めた多様な学問領域をバランスよく配置し、日本において本格的なリベラルアーツを牽引してきたICU。その学びのスタイルは、2004年に開学したAIUにおいても大いに参考にされていたという。鈴木氏はこう語る。「AIUの初代学長・中嶋嶺雄氏はICUの近所に移転して来た東京外国語大学の学長でした。AIUの設立にあたって、よくICUに来られて、リベラルアーツの何たるかを、ここICUから吸収されていました」。
Paragraph 03
ICUとAIU、両大学の違いから
ICUのアイデンティティを考える。
両大学の大きな違いの一つとしてICUにはキリスト教という一つの価値観を掲げていることがある。岩切学長はこう語る。「ICUにはキリスト教という精神的な支柱があります。そのためコミュニティという概念も生まれやすいと思うのですが、AIUでコミュニティを形成するためにどのような工夫をされたのでしょうか」。
AIUでは充実した国際学生寮を整備し、1年次は全員寮生活が義務付けられている。さらに現在、新たな寮を建設しており、完成後には既存の寮と合わせるとAIUの全学生を収容できるキャパシティになるという。
「その狙いは、やはりコミュニティを作っていくこと。学生同士のつながりを深めることは大学づくりにおいて重要だと考えます」と鈴木氏。そして、コミュニティ形成のためには、良い意味で「逃げ場をなくす」、つまり半強制的に共同生活を送りながら勉学に勤しむ環境を作ることが重要だと鈴木氏は主張する。
ICUもキャンパスに寮を持ち、全学生の約30%が寮で生活をしている。手法に違いはあれ、「リビング&ラーニング」というスタイルが両大学のコミュニティ形成に寄与しており、それが世界基準のリベラルアーツ教育の実現にもつながっているのではないだろうか。
もう一つ大きな違いをあげるとすると、それは「言語」の捉え方だ。ICUは日英バイリンガルをベースとした複言語主義。AIUでは英語という単一言語で教育を行っている。
現代のようなグローバル社会において英語の重要性は言うまでもなく、敢えて日本語を用いない教育は、世界を意識する日本の学生にとっては魅力的なのかもしれない。しかしICUでは献学以来、大学のポリシーとして日英バイリンガル教育を貫き、さらに現在は発展的に複数言語主義を採り入れており、その利点について岩切学長はこう語る。
「心理学の先生がおっしゃっていたのですが、18~22歳くらいに脳の構造がそれまでと大きく異なり社会性を獲得するために変化するようです。そして、日本語には高校卒業までに使う日本語とは異なる、いわば『学問用の日本語』というものがあって、それは大学で学ばないと身に付かないんですね。その後の長い人生を考えても、大学時代という特に重要な時期に、英語だけではなく日本語で学問に触れる意義は大きいと感じています」

それに加え、海外から来た留学生に「異文化」を体験する機会も提供したいと岩切学長は話す。「英語圏で育った人が英語で授業を受けてもさほど刺激はない。日本語で学び、『日本語で考えるとこうなるのか』という経験を外国人留学生にしてもらいたいのです」。
鈴木氏はこう反応する。「AIUを新設するにあたって、ICUと差別化したい気持ちは創立者にあったのではないかと察します。そうした考えもあり、『全ての授業を英語で行う』という大方針を打ち出したのだと思いますが、『日本人としての人間教育』という点においては、ICUのような複数言語主義が理想だと私は考えています」。
あらゆる学生の幅広い視野を育む複数言語での学びは、揺らぐことのないICUのアイデンティティであるといえよう。
Paragraph 04
何をもって「世界に通用する」といえるのか。
カギとなる「common good」と「オープンマインド」。
この日、2人に大きな問いを投げかけた。両者が考える「世界通用性」とはどのようなものなのか。
岩切学長は次のように語る。「世界に開かれた『人間性』が重要だと感じます。レベルの差はあるにせよ、世界中のどの大学でも行っている教育や研究内容は大きく変わらないと考えています。つまり、世界共通の問題意識の中で大学は教育や研究を行っているわけです。そうした中で、自分の集団の利益だけを追求していくやり方があるとしたら、どれだけ先進的な研究を行っていても『世界に通用する』とは言えない。グローバルな構造を理解した上で、皆にとって良いものとは何かということをしっかりと考え、心が世界に開かれていることが『世界通用性』だと私は思います」。
この考え方はまさに、2021年度から2025年度にかけたICUの中期計画に登場するキーワード「common good」の精神、そしてICUのカルチャーの一つ、世界に開かれることで当たり前に異質なものとの出会いが繰り返される環境で育まれる「オープンマインド」に直結するものだ。
鈴木氏は、また別の観点からの意見を聞かせてくれた。「ローカリティとグローバリティは対立しながら存在しています。『世界通用性』を考える時、その二重構造に気づく必要があります」。自国のこと、地域のことを知らなければ、「自分」を知ることも困難だ。「地域性を知ることで自分自身を定義でき、また世界を捉えることができると考えています」(鈴木氏)。
岩切学長は「日本の大学の『世界通用性』が低いわけではない」とも話す。「ノーベル賞を受賞している研究者は多いですし、長い歴史の中で蓄積した文化資源も豊富にある。学生の学びへの意欲を見ても、一昔前と比べ、今の時代はしっかりと勉強している大学生が多いように感じます」。

鈴木氏はアメリカで教鞭を執っていた経験から次のように語る。「アメリカでは『クラスパーティシペーション』という学生の授業への参加度を、学生への成績評価項目として設けていました。積極的に質問したり、授業を盛り上げたりする学生が評価されるのは、アメリカでは一般的な形です。そして、授業に積極的に参加するために必要なことは予習。しっかりと予習を行うためには、各回の授業でどのような内容を扱うかが分かる詳細なシラバスが必要です」。
ICUは比較的早期から本格的なシラバスを導入した大学だが、こうしたクラスマネジメントや評価基準に対する考え方を形式的に実質的にも包括した日常的なクラスのあり方こそが、今後さらに「世界通用性」を高めていくためのヒントになるのかもしれない。
Paragraph 05
ICUが成すべき
「リベラルアーツの社会実装」と、その課題。
「common good」の精神を重視するICUの中期計画の副題は「リベラルアーツの社会実装」である。その狙いについて岩切学長はこう語る。「これまでは学生一人ひとりの中にリベラルアーツを組み込んで育てるということを重視してきました。これからはリベラルアーツ的なものの見方や考え方などが、もっと社会に浸透していくような教育・研究を目指していきます」。
ただ、「リベラルアーツの社会実装」は容易な道のりではないことが想像される。リベラルアーツという概念への理解が日本で十分に浸透しているとは言い難いからだ。その要因について鈴木氏は次のように語る。
「明治時代に日本の大学制度がスタートするにあたり、日本の視察団は欧米の大学を参考にしました。当時、イギリスやフランスはリベラルアーツ的な教育を行っていましたが、日本に最も適しているとされ導入されたのは、プロシア(プロイセン)の高等教育が採用していた専門学部教育。それが日本の大学制度の中に生きているのです」
また岩切学長は次のように分析する。「リベラルアーツを正しく理解するには古代ギリシャの時代までさかのぼる必要がありますが、『リベラルアーツ』という言葉のイメージも誤解が生じる要因かもしれません。例えば『アーツ』というと『芸術』や『美術』を連想しがちですが、『技術』や『学問』といった意味もあるんですね。この点をまずはしっかりと伝えなければならない。また、リベラルアーツは『教養』と和訳されることが多いのですが、これも誤解を招く要因の一つではないかと思います」。「教養」と「リベラルアーツ」の定義については、「ICUのコアに迫るふたりのDialogue #03」をご参照いただきたい。
リベラルアーツの浸透に向けての課題は多い。ICUが牽引役となり、リベラルアーツの概念が正しく広がっていくことを期待したい。

[あとがき]
大学が「世界通用性」を高めるために――。
多様性の中での共通の価値。
個別の研究や取り組みで世界に比肩する実績を持つ日本の大学は多い。一方、リベラルアーツが多義的に解釈され、「国際教養」や「リベラルアーツ」を標榜した学部や教育プログラムを開設する大学が散見される昨今、時代に合ったリベラルアーツの再定義が求められている。また、リベラルアーツを冠するプログラムの全てが世界基準の教育レベルに達しているのだろうか。まだまだ課題は多い。
こうした状況の中で、日本の大学が「世界通用性」を高めていくために必要なものは何か。
グローバル・イシューが山積し、SDGsが大きなうねりとなり、新型コロナ禍が襲来した。こうしたVUCA時代において、「common good」の精神を持って、地球上で起きている出来事に目を向け、耳を傾け、対話的に議論を重ねる。多様な価値観を認め合い、その上でどうするかを個人ではなく協働して考えていく。そうした姿勢、人間性が何より重要ではないだろうか。
そして、「理想論」や「机上の空論」で終わらせずに、課題を現実的に共有する。違いをハイライトするのではなく、当たり前と受け止める環境、つまりは、本質的な多様性の中で、全てを包摂的に、解決に向けて実践していくコミュニティが必要なのである。ICUが担う役割は大きい。
関連情報はこちら
Sub Dialogue

“知”が交わる対話録
ICUのキャンパスで目指した「リビング&ラーニング」
ふたりの対話には、語り尽くせないICUへの強い思いが感じられた。
大学の舵取りに尽力した、ふたりの語らいの時間。
大学の役割は「知識の伝達」だけなのか。
コロナ禍の中で、新しい大学のあり方が問われている。
- 岩切学長
- 私がICUに着任した25年前、鈴木先生はすでにICUで教鞭を執られており、教員リトリートというオリエンテーション合宿で同じ部屋だったというご縁がありました。そして、先生はICUの学長を務められていた時、この対談を行っているダイアログハウスの建設をはじめ、さまざまなキャンパス整備に注力されていましたね。
- 鈴木氏
- そうですね。学生寮も私が重視した施設の一つで、ICUの全学生の半数にあたる1500人くらいを収容できる環境を当時は考えていました。「大学の近くに実家がある人も寮に入りなさい」という方針でしたね。
- 岩切学長
- 現在、寮の収容人数は少し減って900人くらいですね。首都圏出身の学生は実家から通う人も多いですし、コロナ禍以降は共同生活を躊躇する人もいます。
- 鈴木氏
- これまでも、ICUのキャンパスのかたちは変化を続けてきました。コロナ禍に入り、「知識の伝達」だけが大学の役割とされると、「キャンパスなどいらないのではないか」という議論にもなってきます。私は「知識の伝達」に加え、「人間性のコンタクトの場」であることが大学の役割だと思っています。今こそ、新しいキャンパスのあり方、大学のあり方というものが問われているのかもしれません。
- 岩切学長
- ICUは人間的なつながりやコミュニケーションを大切にしてきた大学です。その特長を、ウィズコロナ、アフターコロナの時代において、どのように維持し、深化させていくかが大きな課題ですね。
PROFILE

岩切 正一郎 学長
国際基督教大学学長。専門はフランス文学。2008年には第15回湯浅芳子賞(翻訳・脚本部門)を受賞。パリ第7大学テクスト・資料科学科第三課程修了 (DEA)。国際基督教大学アドミッション・センター長、教養学部長を経て2020年4月より現職。

鈴木 典比古 元ICU・AIU学長
国際基督教大学名誉教授であり、元国際教養大学第2代学長。一橋大学経済学部を卒業後、アメリカのインディアナ大学において経営学博士号を取得。その後、アメリカの大学で13年間教鞭を執り、ICUに着任。ICU学長時代には、メジャー制度への移行や学生寮の新設など、さまざまな改革に注力した。
企画制作・執筆協力:株式会社WAVE