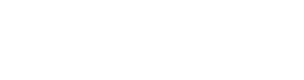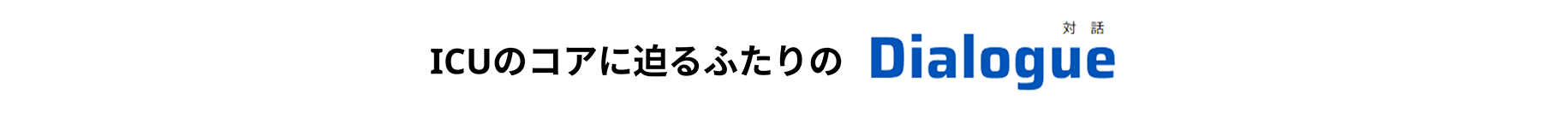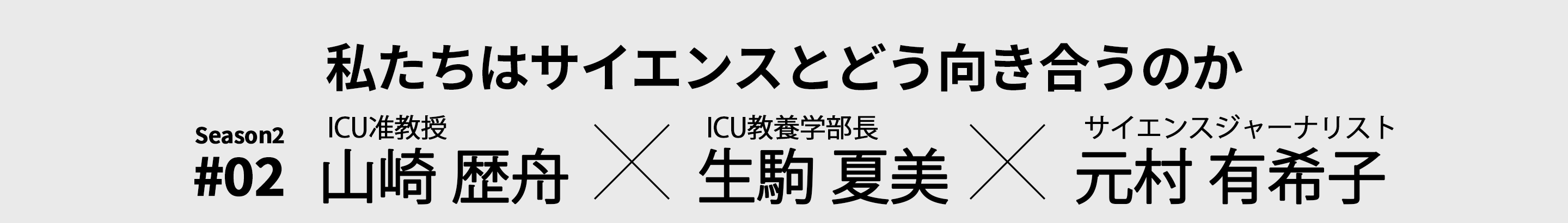
写真:左より、山崎 歴舟氏、生駒 夏美氏、元村 有希子氏
#アーツサイエンス #サイエンスコミュニケーション #サイエンスリテラシー #科学と社会
このDialogueは2025年7月に同志社大学東京サテライトキャンパスにて行われた。
大学全体のカリキュラム責任者である生駒夏美ICU教養学部長、
量子物理学の分野で最先端の研究を行う山崎歴舟ICU准教授と
サイエンスジャーナリストで同志社大学特別客員教授でもある元村有希子氏。
現代社会が抱える課題と科学(サイエンス)。3人が語る「サイエンス」とリベラルアーツとは。
加速度的に発達する科学技術
私たちはサイエンスとどう向き合うのか
人類が突きつけられているさまざまな課題の解決に向け、科学技術は重要であり誰もが無関係ではいられない。生駒学部長は「環境問題や貧困、不平等などの問題解決のために科学的思考力は不可欠」と言う。
その科学技術は、生成AIに代表される情報技術の進化を持ち出すまでもなく、発達のスピードが増すばかり。サイエンスジャーナリストで同志社大学特別客員教授を務める元村氏は「人間が知的好奇心を持つ限り科学の進歩は止まらない」と話し、この状況が将来にわたって続くことを示唆する。しかし、そのスピードの速さゆえ、社会全体がついてこられない面もある。そうした現状について山崎准教授は「科学開発の背景や危険性について語られないことの危うさを感じる」と指摘した。
必要だが危うさも内包する科学技術。では、我々は科学技術とどう向き合えばいいのか。3人の識者が語り合った先に見えてきたのは、科学的な知識や技能、考え方を理解し、日常生活から現代社会の諸問題に適切に対応できる力、つまりサイエンスリテラシーの底上げ。そして、その実現に向けたリベラルアーツの重要性だった。
Paragraph 01
なぜ今、「サイエンスコミュニケーター」が求められるのか
――進歩が速く複雑化する科学技術を市井の市民が理解することは難しい。文系・理系といった区分を当然とする教育が一般的な日本社会においては、なおさらである。そこで注目されているのがサイエンスコミュニケーター。開学当初から人文科学、社会科学、自然科学を網羅するリベラルアーツ教育を実践するICUには、まさにサイエンスコミュニケーターが育つ環境があると言える。その役割と重要性を確認することから対話が始まった。
元村氏 科学と社会をつなぐ架け橋になる人材を育成することを目標に、同志社大学は2016年に「サイエンスコミュニケーター養成副専攻」をスタートしました。特徴は学部横断型であること。生命医科学部、神学部、文学部、社会学部、法学部、経済学部といった6学部の学生に開かれています。もう一つの特徴は学部で開講していることです。他大学の多くが大学院で展開していますが、柔らかい感性をもって幅広く学んでいる学部生のうちに、考え方やスキルを身に着けてほしいという思いがあります。
生駒学部長 ICUでも科学的な思考の取得はとても大切だと考えて、一般教育プログラムで科学的思考を育む学際科目を提供しています。今の社会は細分化してしまっていて、理系の人が話す言葉は文系の人には通じず、逆もまたしかりです。ただそれだと、環境問題や貧困、不平等などの現代社会の問題は解決できません。さまざまな領域の先生や専門家が協力して、お互いに理解し合いながら解決に向けて取り組んでいく時、文理の区分を繋げる考え方が必要だと思います。

元村氏 2005年頃に政府主導で育成が始まった初期、サイエンスコミュニケーターは、ミュージアムの解説員や科学報道に携わる記者など、科学を分かりやすく噛み砕いて伝える人という限定されたイメージでした。今は当時より複雑な社会になっているので、例えば企業の研究者やユーザーとコミュニケーションをとりながらより良い製品の開発に介在する役割などに広がっています。学校の先生もサイエンスコミュニケーターですし、遺伝子組み換え食品の導入や感染症対策など、暮らしと政策の間をつなぐ人材が行政機関にも必要です。
山崎准教授 我々がサイエンスを伝えるのに最初にやらなければならないのは、言葉を揃えることです。ノンサイエンスの学生に配慮して、伝えたいことや使う言葉などを定義して、学生がサイエンスコミュニケーションに慣れるようにしています。ICUの日英バイリンガル教育もサイエンス教育を後押しします。言語が分からない人や文化が違う人と会話するためには、まず共有できる共通基盤を探さなければなりません。ICUの授業ではさまざまな分野の学生が日常的に混ざっているので、その基盤から積み上げていくことを経験している学生は高いコミュニケーション能力が身につきます。
生駒学部長 その通りだと思います。ICUの学生のバックグラウンドは多様です。そのような環境の中で自分の価値観を当然視して発言しないようになっていきます。自分が信じている価値観があっても、それが当然という話し方はしません。「私はこういう理由でこう思うのだけどあなたは?」という話し方になります。そうするとお互いの違いが理解できて、そこから学ぶことはとても多い。ICUにサイエンスコミュニケーター養成のプログラムはありませんが、結果的に育っているのだと思います。逆もまたしかりで、文系の分野を学んでいる学生がサイエンティストに対して哲学の考えを伝えるなどの役割も果たせます。
元村氏 それがサイエンスコミュニケーションの一番の要諦だと思います。サイエンスというと少し堅いイメージがあるので、それをきちんと共有できる形で見せるには、相手の立場に立って自分の考えを伝えるという、コミュニケーションの技術が一番大切なポイントになります。
Paragraph 02
サイエンスは重要。でもそれだけでは不十分
――科学技術の加速度的な発達に対応できるほど、私たちの社会は十分に成熟しているのか。未成熟だとしたら足りないのは何なのだろうか。
山崎准教授 現代は一つの科学技術がクローズアップされ過ぎだと思います。私が開発に携わっている量子コンピューターをはじめ、過去にはSTAP細胞やiPS細胞などの技術も大きくクローズアップされましたが、その本来の怖さやそこに行き着くまでに何があったのかという背景、さらに本当にこの開発を続けていていいのかといった、本質の理解に至っていないことを懸念します。例えば、サステイナブルな世界を目指し、温室効果ガスなどさまざまな問題をサイエンスで乗り切ろうという傾向があります。そのためには高額なコストや膨大なリソースを使った「開発という名の大量消費」を惜しまない。サイエンスは正しくて、科学の進歩によって開発を進めるのがいいといった方向に盲目的に突き進むところに恐怖を覚えます。

元村氏 同感ですね。人間が知的好奇心を持ち、目の前に謎に満ちた自然がある限り科学の進歩を止めることはできないのだけど、立ち止まるという知恵も必要だと思います。温暖化や気候変動、AIによる誤情報の拡散など、科学者だけでは解決できない問題だらけですよね。21世紀は、こうしたトランスサイエンス※1的課題に科学者や専門家と異なる分野の知見を持った人たちが一緒にタックルしていかないといけない。科学の知識ばかりを教え諭すような20世紀のモデルは、一度忘れた方がいいと思います。
生駒学部長 20世紀モデルはそれこそ科学こそが正義であり正しさである、科学は間違えないという理解だったと思うのですが、科学も間違えるし、人間のあり方を歪めることもある。そういうことが、21世紀になって見えてきたということだと思います。科学の追究が18世紀に大きく進んだとき、19世紀初頭に科学への懐疑がとても大きくなりました、それがフランケンシュタインなどの物語に取り上げられているわけですが、もう一回その波が繰り返している今、AIや環境問題、温暖化などで、反省を促されている時なのだと思います。立ち止まって考えるには、リベラルアーツが必要であり、文学や哲学、宗教学などはこれからますます重要になっていきます。
※1…トランスサイエンス:アメリカの物理学者アルビン・ワインバーグが1972年に提唱した概念。原子力の活用や環境問題など、科学的な手法だけでは答えが出ない課題に対し、社会的な価値観や倫理観、政治的な手法などを持ち寄って解決の道を模索する。
Paragraph 03
教育の果たす役割と現状の課題
――サイエンスリテラシーの獲得に不可欠なリベラルアーツ。その本質は文理の壁を取り払って学際的に学ぶことにあるが、日本とアメリカでは差異があるようだ。文系と理系の学生が混ざりあって学ぶための、日本の大学の取り組みとは。
山崎准教授 アメリカには理系や文系という概念がそもそもありません。そういう意識が刷り込まれていないので、例えば心理学を履修しながら生物学を履修する、物理学を履修しながら哲学を履修するという学生が数多くいます。日本では学生が無意識のうちに文理の区分を制限していると感じます。特に数学や物理に苦手意識が強い。また、アートや音楽などは自分の分野ではないと捉える傾向も強いですね。私はアメリカのリベラルアーツカレッジで、宗教や心理学、歴史、物理を履修し、陶芸や音楽理論に没頭した時期もありました。興味が向くままに履修した知識を思考の中でつないでいくというプロセスができたことは、日本とアメリカの大きな違いです。
元村氏 同志社大学のキャンパスは、理系学部が京田辺校地(京都府京田辺市)、文系学部が今出川校地(京都府京都市)と物理的に分かれているので、両者が混じりあうことは難しいのですが、「サイエンスコミュニケーター養成副専攻」では一緒に学びます。実習主体の授業などで文系と理系の学生が席を並べると、言葉遣いから違うことに戸惑うのです。理系の学生同士が話している内容は文系の学生に分からない。文系の学生がアイデアを出すと、理系の学生はそんな考えがあるんだと驚く場面がそこかしこで展開します。高校時代から文化が分かれている中で、大学に入学して少しずつお互いを知る。授業を通して、お互いの考えを取り入れながら自分を磨いていく、あるいは相手が分かるように自分の考えを述べるというお作法を、学生たちが自然と身につけていくのが手に取るように分かります。
山崎准教授 ICUでいうと、一般教育科目にジェンダーや国際関係、心理学、自然科学など、異なる分野の先生と学生がディスカッションする「ポストヒューマン」の授業※2があります。それぞれ異なる専門の切り口で議論することにより、学生に学問領域を超えたコミュニケーションの面白さや大切さを見せられていると思います。
元村氏 ポストヒューマンの授業、私も受けたいです。人間は学び続ける動物だと思っていて、研究者は一つの専門を極めようとひたむきに努力しますが、研究者である前に一市民であって、自然の一部を構成している生物ですよね。それこそ専門外のことに関しては素人なわけで、知らなくていいというのではなく、学び続けていく大人たちの姿勢が学生に見えるというのはとても意義深いことだと思います。
――学際的な思考が求められるのに学部で縦割りにされる日本の大学。教養学部として大学全体で、文理を超えて学生が混ざり合う環境でリベラルアーツを実践するICUの強みとは。
元村氏 今の学生を見ていると、想像以上に凝り固まっているなと思うことがあります。文系と理系に分けられて受験勉強をしてきた結果、自分が属する世界以外のことは勉強しなかったし、これからもしなくて済むだろうと思っている。これでは興味を持ちようがない。入学すれば、次のゴールである就職が視野に入ります。就活に役立つことには熱心だけど、それ以外は二の次と考えているようにも感じます。そうした学生たちには、「就活が大事なのはわかるけど、その先の人生の方がはるかに長い。あなたたちは多分21世紀の終わりを見るから、その時に自分が幸せだったなと思えるような学びを今のうちにやってほしい」と伝えています。
生駒学部長 ICUの場合は、最初からこれをやると心に決めて入ってくる学生と、まだ決まっていないので入学後に専門を決めることができるからICUを選びましたという両方の学生がいます。そういった学生が教室で混ざり合う中で、最初から私はこれに決めていますという考えが崩されて、最初と違う学問分野の方が好きだったと発見する学生が出てくるところが面白いですね。
山崎准教授 先ほどのポストヒューマンの授業は、一般教育科目ということもあり、1年生から4年生まで、またいろいろな分野の学生が混ざり合いやすいコースです。上級生がいろんなことにチャレンジしたり、自分が考えないような授業を取っている姿に、下級生が刺激を受けているといったこともICUの文化と言えます。

生駒学部長 教養学部一学部だけという良さはあると思います。どこかに振り分けられずに大学全体で1つの集団を作っています。特にICUの一般教育科目は、日本の大学のいわゆる「一般教養」とは異なり、卒業まで満遍なく取ることになっているので、卒業間近の4年生も、入学したての1年生も一緒にディスカッションすることになります。すると、上級生は一生懸命説明することで知識を確認するいい経験になる。下級生にとっては、頑張ったら上級生のようになれるというロールモデルになっています。
――大学全体でリベラルアーツの本質を極めるICUだが、そこに課題はないのだろうか。
元村氏 子どもをICUに通わせることのできる家庭は、経済的な面も含めて限られていますよね。親の意識が高く、学生たちはすでに高校までにいろいろな経験をしてきている。ICUはある意味、リベラルアーツの「エリート」を養成する教育機関と言えます。そういう恵まれた環境だからこそ、思う存分、勉強や考えの異なる人と議論できるのだという現実を学生が認識することがすごく重要です。高い理想を持って社会に出て仕事を始めれば、正論が通らなくてがっかりすることはたくさんあります。平和を願う市民として自分は活動しているのに、政治や国際情勢が全然違う方向に行くとか。そういったことに絶望したりあきらめたりするのではなく、根気を持って粘り強く、しぶとく取り組む資質まで、学生時代に身につけてほしいと思います。
生駒学部長ICUの学生が多様性を身に付けるプログラムとして「サービス・ラーニング※3」があります。ICUという非常に恵まれた環境で培った知識を使って、どのように社会に貢献できるのかについて体験し単位を与える仕組みです。途上国に小学校を作るなど、国内と海外のプログラムがあって多くの教員が関わっています。このプログラムを通して、学生たちは途上国の現場で価値観がひっくり返る経験や、正論だけでは何も動かせないということを身を持って体験してきます。
※2…一般教育科目「ポストヒューマン」:ICU入学案内「リベラルアーツから問う ポストヒューマン」
※3…サービス・ラーニング:自発的な社会貢献をめざすボランティア活動を通した学び。社会のさまざま課題に対して他者と目的を共有した上で自分事として取り組み、その課題に関する既存の知と自らの経験から得られた学びを結び付けることで、新たな考え方や行動の仕方、自分自身のあり方を省察(リフレクション)しながら発展させる経験的学修プログラム。
Paragraph 04
リベラルアーツ教育は未来を創る
――中等教育を文理の区分で学んできた生徒たちが大学に入学してくる現実の中、高等教育ではどのように学生を育てていくのか。特にリベラルアーツは課題を自分ごとと捉え、社会との繋がりの中で追究していく学びともいえる。不確実な未来を生きる学生たち、文系学生にも理系の素養が求められる今、リベラルアーツカレッジにおける文系学生に対するサイエンス教育の取り組み事例とは。
生駒学部長 これからの時代に不可欠な統計の読み方などの数理系のスキルを身に着けることを重視しています。文部科学省が認定する「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」の導入以外に、ただ知識を与えるだけではない、ICUらしい手法も採用しています。例えば情報科学あるいは数学の先生と社会学系の先生が組んで、実際に社会で使われている統計などを扱いながら学ぶ授業があります。数理系のスキルをきちんとつけながらその応用を重要視しているのです。

山崎准教授 サイエンスに関する教育レベルが異なる国からの学生も多いので、そういった学生がギャップを感じないように、初級コースはすごく易しくしています。そういうクラスは自然科学系以外をメジャー(専修分野)としている学生もよく履修します。教養としてさまざまな学生が履修している分、ハードルを下げて取り組みやすくしています。
生駒学部長 教養学部長として自然科学系の教員にお願いしているのは、理系以外をメジャーとしている学生も面白いと思える授業を作ってくださいということです。高校で嫌いになってしまった学生にも、大学で面白いと感じてもらえるような授業を展開しています。いわゆる高校までに文系の教育を受けてきた学生が理系の授業で躓いたとき、学部生のラーニングサポーターがフォローする、Qサポ(Quantitative Skills Support)という制度もあります。
――リベラルアーツカレッジであるICUの自然科学系メジャーの教育は、どのように展開しているのだろうか。
山崎准教授 ICUの自然科学系メジャーでは、純粋理学を押さえた上でその後のチョイスの一つにエンジニアリング(工学)があります。自然科学の基礎を学んだ上でテクノロジー(技術)を学びたい学生は、ICUを含めた国内外の大学院に進学しています。量子に関する私の研究室を卒業した学生も、基礎物理を学んだ上で、イギリスで航空工学の研究をしたり、東京大学の海洋研究所で研究をしたりしています。
元村氏 キャリアが多様ですね。基礎科学を学んだ上で、その素養と広い視野を武器に専門を深めていくというモデルは大事だと思います。これからますます科学が社会に影響を与えていく時代になりますから、科学を引っ張る人たちの資質や意識がとても重要になります。もう少しかみ砕いて言えば、自然に対する謙虚さ。自分の仕事は「巨人の肩の上に乗っているだけ」という意識はすごく重要です。狭い専門分野で成功したからといって、過剰な万能感を持って他者との競争に突き進むような態度では、うまくいかないのではないでしょうか。
山崎准教授 科学技術の進歩により科学のグローバリゼーションが進み、いろいろな技術が世界中に広まるようになったことで、科学が引き起こす弊害も増えてきています。科学が社会に出て人に使われるときに生まれる問題に対して、科学の知見だけでは対応できず、人文科学や社会科学の知見から見直さないと、何が問題なのかさえ分からないことがあります。そうした背景からMIT(Massachusetts Institute of Technology、マサチューセッツ工科大学)では、人文科学や社会科学にも力を入れています。ICUのアプローチもそれに近いですね。科学を学びながら他の視点を持って科学にタックルできる見方がこれから求められていくと思います。

元村氏 まさにトランスサイエンスと呼ばれている状況ですね。この概念が提唱された1970年ごろの世界は、どの国も不思議と共通しているんです。米ソが核軍拡や宇宙開発に巨額のカネをつぎ込みしのぎを削る中、ローマクラブ※4が「成長の限界」を発表し、アメリカでは公民権運動が盛んになる。日本では公害問題が深刻化し、人々が科学技術の進歩に疑問を持ち始めます。それを如実に表していると思うのが、統計数理研究所が5年ごとに調査している「日本人の国民性調査」です。この中に、自然と人間の関係※5について尋ねる質問があります。 1968年の調査では「自然を利用する」に続いて「自然を征服する」が2番目、「自然に従う」が最も少ない結果でした。ところが1973年には「自然に従う」が「自然を征服する」を抜き、順位が逆転しました。50年後の最新の調査結果は「自然に従う」が最も多く、「自然を征服する」を選ぶ人は1割もいません。
生駒学部長 60年代後半にはベトナム戦争がありました。人間の欲望がいく行き着く先が示されたと言うこともあるのでしょう。枯葉剤という科学が生み出したものが、人を絶滅させかねないという考え方がでてきたのでしょうね。
※4…ローマクラブ:スイスに本部を置く民間のシンクタンク。
※5…「自然と人間の関係」:自然と人間の関係について、次の質問項目から一つ選んだものを集計したデータ。
質問項目:「人間が幸福になるために」①自然に従わなければならない。②自然を利用しなければならない。③自然を征服してゆかなければならない。
Paragraph 05
よりよい社会に向けて、我々はサイエンスとどう向きあうのか
――文部科学省から高大接続の重要性が示され、中等教育と高等教育の教育接続について語られる機会が増えている。現状の入学者選抜の在り方が問題視されることも多いが、教育の本質的なところに立ち返って我々は何ができるのだろうか。高校生がサイエンスと向き合うようになるための教育の課題はどこにあるのだろうか。
元村氏 科学は客観性をすごく重んじるけど、主観から始まる科学教育があっていいと私は思います。例えば、日高敏隆さんの「チョウはなぜ飛ぶか」というエッセーでは、日高少年が自然に関心を抱くようになった体験がつづられています。いつも庭に来るモンシロチョウが、いったいどこから来てどこに行くのか。それを調べる中でモンシロチョウの生態が見えてくる。チャットGPTに聞けばすぐに教えてくれる平板な知識ではなくて、主観的な問いから始まる学びです。こんなワクワクするような授業が、全国の教育現場で行われているでしょうか。理科離れの原因は、そのあたりに潜んでいるように思います。
山崎准教授 日本のサイエンス教育はアメリカよりも圧倒的に早いんです。大学受験までもそうだし、大学でも結構早い。アメリカでは大学院に入るための物理のレベルはそれほど高くはありません。アメリカでは高校の間に物理を取らない生徒も多く、大学から取ってみようという学生もいます。嫌いになるまで押し付けられないんですよね。日本ももう少しゆとりを持っていい。詰め込み過ぎだと思います。
元村氏 学習指導要領は浅く広く学んで大学受験に備えるためのものに感じます。「科学立国日本をけん引する人材は何歳までこれを覚えておかなければいけない」という押しつけがましい発想が根本にあると思います。誰もがそういう人材になるわけではないのに。
山崎准教授 そういう詰め込み教育は、研究者になるための正しい資質をまったく育てていないと思います。私はポスドクとして大阪大学、京都大学、東京大学といった国立大学で働いていましたが、どの大学でも大体トップ10%から20%の学生が、とてもハイレベルな研究をしています。どの大学も同じ割合で出てくるので、入試で測っている学力はあまり研究と結びついていないと感じました。何が違うのか考えて思ったのは、優れた研究者になる学生は「気付く」能力があるんです。ただガリガリ勉強をやるというよりは、どちらかというと、ふわーって考えた時に「気付く」。推薦で早く合格を決めた高校生が入学まで何をしたらいいのかと尋ねてきた時、今まで勉強してきたんだから、森で遊びなさいとよく言っています。森に行くと予想しないところに枝が落ちていたり、葉っぱが溜まっていたり、虫がいたりします。その中から子どもたちはいろいろと「気付く」んですよね。こういうサイエンスの教え方をなぜしないのかとずっと思っています。そうしたことを飛ばして事実だけを教えてしまうと、「気付く」能力が育まれないのではないでしょうか。
生駒学部長 日本の受験勉強は本当によくないと思っています。これを学ばないとダメだと詰め込み式で学ばせて、自由に発想する余地を奪ってしまっています。ICUの一般選抜※6はそういうのではないのですが、今度は逆にどうやって勉強したらいいのか分からないと言って敬遠される。対策は立てなくていいと言ってるんですけど、それが怖いのですよね。詰め込み式の勉強は今の教育の弊害だなと思っています。
※6…ICUの一般選抜:一般的な学力試験ではなく、教科融合型の「人文・社会科学」または「数理・自然科学」のいずれかと、講義を聞いた上でその内容に関する設問に解答する「総合教養(ATLAS)」、英語の3科目で実施。リベラルアーツへの適性を見る能力試験。
――対話の最後に。これからの世界を創る若者を育てるために大学ができることについて語り合った。

生駒学部長 今の日本の教育制度の中で考えると、文理を分けた教育システムが生み出すネガティブなインパクトを、大学で払拭して改めて可能性を拡げることで、大学では自由に知的好奇心を伸ばす機会にしてほしい。社会に出る前にそれをしておかないと、そこから先は自分の専門性を研ぎ澄ます方向に進むしかありません。社会に出る前に知識を統合していくことが重要だと思います。こうした観点から、これからも大学におけるリベラルアーツ教育の重要性は増していくと思います。
元村氏 学生に対して、「世の中はあなたたちが思うよりずっとずっと複雑である。だけど、あなたたちの力で変えていけるものなんだよ」と始終言ってます。大学の4年間で、社会で生きていくための基礎的なスキルを一緒に学びましょうというスタンスでいます。私はサイエンスコミュニケーションを教えていますが、科学的なものの見方や数字の読み方など、科学を使いこなし味方につけることで自分を守り愛する人を守れる。その手段がサイエンスコミュニケーションだと伝えています。
もうひとつ、現状で物足りないのは、日本国民は社会福祉や公共事業、政治とカネといった問題には積極的に発言しますが、科学のことになると途端におとなしくなるのです。現代社会は、科学が駆動する分野が多いという現実に気づいてもらいたい。これからの社会を担う若い人たちには、科学研究が税金で賄われているということを前提に、適切に口を出せる市民になってほしい。サイエンスコミュニケーションはそのためのスキルであり、ひいては民主主義を健全に機能させる基本的な装置になると考えます。幸いなことに、学生たちは地球の持続可能性や多様性の問題への関心が高く、大人が思っているよりずっと賢明です。自分たちや世界の人々が健やかに22世紀を迎えられるのか、ということにも強い関心を寄せています。大学での学びを、そうした問題意識とうまく結びつけられたら、彼ら彼女らは自分で動き出すと思います。希望を捨てていません。
山崎准教授 大人の教員と若い学生が一緒に教育や研究をすることに意味があると思っています。大人は方法論は分かってるのですがアンテナが鈍ってきています。一方若い人は、環境にとても気を配っていたり、社会の情勢をすごくよく見ていたりします。そういうところで鋭いアンテナを持っている学生から出てきた良いアイデアをいかに我々が組み上げられるかが大事です。学生たちに、「君たちが感じていることは本当に意味があるものなんだ」と伝えることが教育のあり方ではないかと思っています。私たちが教えるというよりは、学生が各々の豊かな感性で現代を見つめることを私たちの方法論でうまくガイドするという共同作業が求められていると思います。
生駒学部長 ICUとしては学生が経済的に成功するためにとか、学生自身の未来のためだけに育てているのではなくて、社会全体とか地球全体のため、世界で活躍して変える人になってほしいという願いがあります。そういう意味では、やっぱりサイエンスは本当に必須の視点だと思いますので、そこをICUとしてうまく伝えていきたいと考えています。
【対話を終えて】
市民のサイエンスリテラシーの高い社会を目指して
サイエンスリテラシーは重要。しかし、一朝一夕に社会に行きわたるものではない。その伝播のスピードは大学教育にかかるが、元村氏は、大学生の科学的思考力の壁を危惧する。
「“科学技術って何?”と聞くと、“テクノロジーです”と答える学生が多いことに驚かされます。つまり、科学的知識をもとに発明した技術を科学技術と考えているわけです。実際には、科学と技術は別物で、英語でもサイエンス&テクノロジーと表現します。知的好奇心に基づいて自然をひもといていく営みが科学であり、役に立たないから無駄だという価値観とは無縁なのですが、そういうことをきちんと教わっていない。これでは科学的なものの見方や思考力を身に付けるのは難しい」
こうした学生の意識を大学で変えてサイエンスリテラシーを身に着けさせるには、縦割りの学部教育では難しい。そこで注目されているのがリベラルアーツ。献学以来、大学全体でリベラルアーツを展開するICUの取り組みについて、生駒学部長は語る。
「学生は、文理を問わず一般教育科目や関心のある科目を履修しながら、2年生の終わりまでにはメジャー(専修分野)を決めます。メジャーを決めた後も自分の選択したメジャー以外の授業も自由に履修でき、自身でテーマ設定をした卒業研究(卒論)を学際的に掘り下げていきます。日英バイリンガル教育ということで、英語をバックグラウンドとする学生は日本語開講の授業、日本語が第一言語の学生は英語開講の授業履修が必須など、学問領域だけにとどまらず、言語的にも文化的にも社会的にもさまざまなバックグラウンドを持つ学生が日常的に混ざり合って学べるシステムになっています。時には敵対する考え方を持つ人もいるかもしれませんが、お互いに考え方を深めて理解し合ってすり合わせることができる人がコミュニケーターであり、ICUが育成する地球市民です」。
人文科学、社会科学、自然科学を網羅する学際的な学びに加え、多様なバックグラウンドを持った学生が集うICUは、「気付きの場」であり、サイエンスリテラシーを持った市民の育成に貢献している。
対話の余談
科学の本質に触れた新聞記者時代のエピソード
- 元村氏
- 毎日新聞社科学環境部在籍時に立ち上げた「理系白書」の連載でICUの風間晴子教授(名誉教授)に取材した際、「科学は枝葉の部分ばかり注目されるけど、実は幹とか根っこがすごく重要で、リベラルアーツはその根を張る土壌を作る営みなのです」と教えていただきました。こういう考えを科学環境部記者の初期に知ることができた点でICUに恩を感じています。
- 生駒学部長
- 元村さんが記者時代にもっとも興味をひかれたサイエンスの分野はありますか?
- 元村氏
- 素粒子ですね。宇宙から飛んできたニュートリノをつかまえて2002年のノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊さんは、研究者としての情熱をもって周囲を動かし、巨大な観測装置を築きました。誰も思いつかないアイデアを途方もないプロジェクトに結実させ、未知の分野に挑み続ける科学者のあくなき探究心にわくわくしました。あの取材を通して科学の本質に触れられた気がします。
- 山崎准教授
- ニュートリノっていうのは本当に純粋な物理で、社会的な応用こそ無いけれどロマンがあるんです。科学者は本当にそこに山があるから登るのです。社会的に役に立たなくてもそこに行くのが科学者なんですよね。
- 元村氏
- 役に立たなくても、その謎を突き詰める過程で新しい天文学の扉が開かれ、この宇宙にあふれる膨大な謎を解く鍵が増えていくのです。一つ疑問を解いたら次の疑問が現れる、そんなエンドレスな科学の世界を垣間見ることができました。
- 生駒学部長
- サイエンスの面白さはそういうことだと思いますが、それが今の理系教育でできていないので理系嫌いの高校生を生み出す。それはとても残念なことです。ICUではそういう面白さを、感じてほしいという気持ちがありますね。
PROFILE

元村 有希子
サイエンスジャーナリスト
九州大学教育学部卒業。毎日新聞科学環境部記者としてノーベル賞、宇宙開発、東日本大震災・福島第1原発事故などを取材。2006年、『理系白書』の報道で第1回科学ジャーナリスト大賞を受賞。科学環境部長、論説副委員長などを経て24年春から同志社大学特別客員教授。他に高エネルギー加速器研究機構理事、九州大学理事。テレビ、ラジオなど多様なメディアを通じて科学リテラシーの底上げに取り組む。著書に『カガク力を強くする!』(岩波ジュニア新書)、『科学目線』(毎日新聞出版)など。
生駒 夏美
国際基督教大学 教養学部長
国際基督教大学教授。2002年ダラム大学博士号(Ph.D.)取得。国際基督教大学ジェンダー 研究センター長、同文学研究デパートメント長を歴任。専門分野はジェンダー、ヨーロッパ文学、 文学一般、日本文学、思想史。2022年4月より現職。
山崎 歴舟
国際基督教大学 准教授(物理学)
国際基督教大学准教授。ゴーシェン大学教養学部卒、パデュー大学大学院理学研究科修士号取得後、2006年同大学院博士号(Ph,D.)取得。専門分野は量子エレクトロニクス、量子情報。2022年から内閣府のムーンショットプログラムで量子メカニカルメモリの開発を担当している。