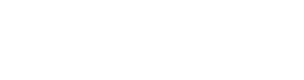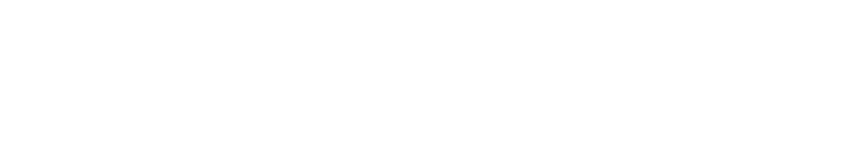鮮やかな復活を果たしたソニー。
再生の立役者である平井一夫氏と、
ICUの竹内弘高理事長が、時代背景は異なるものの
同じキャンパスで学んだ二人が対話した。
#異端 #マイノリティ #アイデンティティ #Common good #コミュニティ
“Agree to Disagree”
「異端」を受け入れる、リベラルアーツの真髄
日本の教育の特徴が、「詰め込み教育」と批判されはじめて久しい。
新しい学習指導要領のスタートにより、その変容に注目が集まったが
標榜する「主体的・対話的で深い学び」の実現は、道半ばであろう。
それでは、果たして「主体的・対話的な学び」とはどのようなものか。
また、どのような力が育まれ、どう人生に役立つのか。
この問いに対する答えのヒントは、今回の対談に隠されている。
大学時代をICUで過ごした平井一夫氏と竹内弘高理事長。
巨額の赤字といった苦境から「ソニー再生」を成し遂げた平井氏。
その成果は、2017年度の決算において「20年ぶりの過去最高益」として現れた。
他方、野中郁次郎氏との共著『知識創造企業』で多くの企業に示唆を与え、
ハーバード・ビジネス・スクールに初めての日本人教授として着任し、現在も教鞭を執る竹内理事長。
今回は二人の対談を通じて、
VUCA時代という逆境を乗り越えるための秘訣を紐解く。
Paragraph 01
「異端」としてさらされること。
それは、逆境であり、チャンスでもある。
組織のリーダーが自身の考えに対する賛成意見だけを尊重していては、「裸の王様」になることは明らかである。ましてや新たな発想やイノベーション、そして重大な過ちや気づきは得られないであろう。批判も含めて異なる意見を受け入れ、その上で明快なビジョン・方針を示す資質が、VUCA時代と呼ばれる現代においてリーダーに求められている。
平井氏の著書『ソニー再生 変革を成し遂げた「異端のリーダーシップ」』(日本経済新聞出版社刊)において、平井氏は異なるものの見方を「異見」と表現し、自身の経営において歓迎していたと記す。そんな平井氏が「異端」を強く意識をした経験は、幼少期までさかのぼる。
「海外転勤続きの父の影響で、幼い頃からアメリカやカナダなど世界中を飛び回る生活でした。どこにいても、常に異端。英語も不慣れなまま飛び込んだアメリカの現地校では“Japanese”として異質な存在で、帰国後に小学校に登校した際に『いつも通り』一週間分の宿題をまとめて提出すると、返ってきたのは『ここはアメリカじゃない!』という教師の一言。『ああ、ここでも自分は“違う”存在なのだ』と感じたことを覚えています。」

1950年代、現在と比較して国際化が進んでいなかった当時、インターナショナルスクールに通った竹内理事長も同様で、「小学校に上がる時に日本の幼稚園の同級生からは『ヒロちゃん、変な学校に行っちゃった』と言われました」と振り返る。一方で、竹内理事長はこうも続けた。
「周りから変わっている、と言われることを敢えて『気持ちが良い』と思うように心がけていました。注目を集めることは、裏を返せばチャンスですから。近所の友達にとっては、僕は変わった存在。そうした相手からの視線や壁を乗り越えて、うまく交流していましたね。」
異端、マイノリティとして歩んできた二人を歓迎し、受け入れたのは、ICUであった。「ICUに入学して初めて、『マイノリティ』の重みから逃れることができた」という平井氏の言葉に、多様性を重んじるICUの特性がよく表れている。
ICUは学生や教員のバックグラウンドや考え方が非常に多様性にあふれていて、皆違うことが当然。「私のようにアメリカの学校と日本の学校を経てICUに行った人もいれば、入学直前までアフリカにいた人、ヨーロッパにいた人、はたまたどこにも行っていない人……。それぞれ異なることが極めて自然であり、それを受け入れる環境がありました。自分が『アウトサイダー』ではない環境に身を置いた、初めての経験でした」と平井氏は語る。
ICUが多様性を重視する理由は、献学の理念を参照すると理解しやすい。第二次世界大戦への深い反省から、「国際的社会人」を育成することを目的に献学。国際的社会人とは、開かれた価値観を持ち、国内外の人々を協働して人類の平和と共存に貢献する人物だ。その育成には、異なる国籍、人種、文化等の価値観を認め、尊重し合うマインドの習得は欠かせない。ICUがさまざまな入学者選抜制度を設けて、国内外から広く学生を受け入れ多様性を確保している背景の一つである。
「ICUにはそもそも、多数派・少数派という概念自体が存在しません。皆が同じ意見を持ってまとまると、むしろ『何かおかしいぞ』と違和感を覚えるような環境。多数派であることを好む文化とは、当時から一線を画していた」(竹内理事長)。
「異見」を歓迎こそすれ、自分とは異なる意見を排除せず議論を尽くす。平井氏の経営哲学にICU時代の経験が影響したことは明らかであり、特に多様性の尊重という側面に対する安心感は大きかったであろう。また、人々が「異端」として、もしくは「ユニーク/異質/マイノリティ」として周囲の目線に晒されるのは、決してポジティブな側面だけではない。しかし、萎縮するのではなくチャンスと捉えられるかは、当人の人生における岐路になると言っても過言ではない。
つまりこのパラグラフにおける示唆は、大学や企業等の組織運営における「環境・場づくり」の重要性に帰結する。組織の構成員それぞれの異見が尊重され、逆境をチャンスと捉えられるようなカルチャー。それを有するコミュニティの形成が重要と言える。
Paragraph 02
多様性を受け入れるICUコミュニティの妙。
設計された「異端」との出会い。
ICUの学生には、それぞれの「ホームベース」があると言われる。「本館前の芝生広場や図書館など、その場所を核にして授業やサークルの活動などに出掛けていく。私にとってはD館がそうでした」と、平井氏は振り返る。
D館(ディッフェンドルファー記念館東)は、建築家ヴォーリズによる設計により1958年に竣工。講堂(オーディトリアム)や学生クラブ活動室などがあり、日本初の学生会館として多くのICU生の憩いの場となってきた。1969年入学の竹内理事長と1979年入学の平井氏。在学期間こそ重ならないが、実は二人の共通項はこのD館にあった。
平井氏は「普段は話さないような人たちと出会う機会が多く、彼らとの対話が楽しかった。実のある話をすることもあれば、そうじゃないものも含めて、かけがえのない時間でした」と語る。 自宅からの通学生だった平井氏にとって、寮生の友人や音楽や演劇などの文化活動に打ち込む学生との時間は、新たなる「異端」との出会いの連続だったのだろう。

平井氏の言葉に呼応して竹内理事長も続ける。「D館での出会いは、設計されていたようにも思います。郵便局があったり、コーヒーを売っている自動販売機があったり、いつの間にかそこに足が向く動線・設計になっている。本館から芝生広場を通ってD館や大学食堂、学生寮へと続く細い道のあるキャンパス。単に多様な学生を集めるだけではなく、彼らを出会わせ、化学反応を起こさせる。そういったキャンパスでの出会いを自然に創出させる『場』としての意図が、設計当時にあったのではないでしょうか。」
同時に、D館は対話の幅を広げる「Arts(ここでは狭義の芸術分野)との出会い」が設計された場でもあった。演劇・音楽を始めとした部活動の場があり、オーディトリアムではコンサートや発表なども行われた。「空いた時間にD館を訪れると、発声練習やエレキギターの音色が聞こえるのです。常に芸術や文化に触れられる場としても大事な場所でした」と振り返る平井氏。「私も当時ピンチヒッターとして演劇部の活動に参加したことがありました。今思えばこのとき演劇に触れたことは、ハーバードビジネススクールで教員として評価につながる経験だったと思います。音楽・演劇・映画プロデューサーの奈良橋陽子さん(1969年卒)ともD館でよく語らいましたね」と竹内理事長が返す。二人の対話からは、時間を越えて同じ場所を訪れ、芸術を通じて交わり合う光景が浮かび上がる。
D館は、老朽化により大幅な改修工事が検討されたが、最終的には独自の意匠や機能の継承・復元に重点を置き2021年に修繕を終えた。二人が過ごした当時の面影もしっかりと継承され、現在もなお「異端との出会い」が自然とあふれる場となっている。
さらに、偶然性が高い出会いの設計は、2023年4月に開館する新館「トロイヤー記念アーツ・サイエンス館」にも受け継がれる予定だ。現・理学館にある研究室や実験室、人文・社会科学系の研究所が移転。約300人を収容する学内唯一の大教室や学生の憩い・交流の場となるカフェテリアなども設置する。そして、アーツ・サイエンス館の完成により、教育建物に囲まれた新たなクアドラングル(中庭)も誕生することも大きい。
あらゆる学生に利用する機会を提供しながら、ガラス張りの実験室やオープンラボスペースといった空間の工夫が施されたアーツ・サイエンス館の設計。それにより、リベラルアーツにおけるサイエンスの学びが全ての学生の日常に溶け込み、思いがけない発見や出会いを生み出すことを狙っている。日本で類を見ないリベラルアーツ・カレッジのユニークさを体現する場となることが想像できる。
偶然性の高い出会いが生まれるコミュニティの妙。これにより対話が活性化し、「多様性の尊重」を担保している。正に新学習指導要領が掲げる「対話的な学び」を実現する重要な役割をコミュニティの設計部分が担っているのである。
Paragraph 03
「自分自身の意見がないと、サバイブできない70分間」。
学生の主体性を担保する、「心理的安全性」。
「異端」との出会いの場は、ICUにはさらに多く存在する。例えば、授業である。専任教員一人あたりの学生数18人(2022年10月1日現在)と、献学当時から少人数教育を貫くICU。大勢の学生に対して教員が話をするのではなく、学生同士や教員がディスカッションを重ねる。そのやりとりの中で、自身の考えを整理し、他者に伝える力が育まれるのだ。
当時の授業について振り返り「先生が一方通行で何かを言い、それを聞いて終わる授業はほぼありませんでした」と平井氏は語る。対話を重んじるICUの授業では、自分で考え、話すことは必須だ。思考をとめどなく続け、意見をまとめて他者に伝えることが求められる70分間。
この教育について「アメリカの家庭教育に類似したカルチャーがある」と竹内理事長は指摘する。「家族で食事をする際、お祈りから始まり1日の出来事を話す食卓では、両親が子どもに“What do you think?” と意見を求めるのが文化として根付いているのです。常に考えること、自分の意見をアウトプットすることを求める側面は、ICUと同様です。」

授業では、相手の意見の受け止め方も学ぶ。大前提として、相手の意見をしっかり聞くことと、それが「異見」であったとしても受け入れるということだ。少なくとも自分とは異なる意見を廃除せず理解しようとするマインドセット。
この考えを二人は、“Agree to Disagree”という言葉で表した。「賛成しないことに賛成する」、つまり意見の相違を認めるということだ。
「さまざまな人と議論をしていると、どうしても“Agree”できない部分が出てきます。だからといって人格を否定したり、打ち負かしたりするのではなく、自分なりのロジックを伝えながら相手の意見に“Agree”できないことを丁寧に伝える。相手の考え方に対するリスペクトはもちろん必要です。最終的にお互いが同じ結論に着地できなくとも、それで良い、と思えるようになりました」と語る竹内理事長。
平井氏も、ICUにおける授業での学びが経営において生かされたことを振り返る。「組織において、“Agree to Disagree”を各メンバーに実践してもらうためには、マネジメント層による工夫が必要です。例えば、会議の場で大多数とは違う意見を発言してくれた人には、その採用可否に関わらず『よくぞ言ってくれた』と、経営者の立場として感謝とリスペクトを伝えることを意識していました」。
こうした組織運営によって「心理的安全性」が高い組織が実現されると平井氏は強調する。「心理的安全性」は、学生の主体性が求められる現代の高等教育においても重要と言える。そして、やはり新学習指導要領が掲げる「主体的な学び」の実現のヒントとなるであろう。
Paragraph 04
リベラルアーツと「真善美」。
VUCA時代に光を示す、普遍的な人間力。
これまでのパラグラフにおいては、「対話的な学び」「主体的な学び」を実現する上で、『コミュニティの妙』や『心理的安全性』といった要素の重要性について紐解いてきた。最後のパラグラフでは、その2つの学びがどのように人生に役立つのか、という観点で二人の思考を深掘りする。
「ICUの4年間で学んだことのひとつが、『リーダーたるもの、人格者であれ』ということです。世界には多様な文化に基づいたそれぞれのリーダー論がありますが、人格者という要素は世界共通です」と語る平井氏。
そして、「繰り返し伝えているのは、さまざまな経営戦略を駆使する前に『リスペクトされる一人の人間』であって欲しいということ。どんなに大きな組織でも、細分化するとすべて人です。多くのメンバーからリスペクトされる人こそ、リーダーに相応しいと思います」と重ねた。
『リスペクトされる一人の人間』。これに関連する言葉として「真善美」という言葉がある。知性と意志、感性を極限まで高めた先に備わる普遍的な人間力を表す。普遍的な価値を見極めるという点において、突き詰めるとICUのリベラルアーツの学びともつながる。
平井氏の真善美の力が如何なく発揮されたのは、ソニーの社長就任後、向かうべき方向性を世界中の社員に対して示した「KANDO(感動)」という言葉ではないだろうか。敢えて英語に置き換えず日本語・ローマ字を採用した選択、異質な言葉とすることで社員全員に思考を求めるという狙い、そしてこの言葉を浸透させるべく世界中の拠点をめぐりタウンホール・ミーティングでトップ自らが伝えるという行動。平井氏の人生における経験値や経営哲学といったすべてが帰結し生まれた言葉「KANDO」は、正に真善美の賜物であろう。
VUCAという言葉が表す通り、新型コロナ禍の影響が未だ残る現在は「先行き不透明の時代」だ。そのような時代を生き抜く上で、対話や主体性が欠かせないことは明らかであるが、やはり真善美を備えた人間力を持って、普遍的な指針を示す資質は重要であろう。
ICUにおいて、このような人格形成をする上で重要な役割を担っているのは「国際性」の特色だ。ICUの国際性について、平井氏は次のように語る。
「ICU生は当時から、ジオポリティックスとか国際連合の動きにも関心が強く、仲間同士の話題にも頻繁に上がりました。私は特に国際法を勉強していたので、国と国がどのように平和を維持していくのか、という思惑や動きには注目していましたし、同じような仲間が多かったですね。ワールドワイドな視点で世の中を良くしたい、という想いを持っている学生が多いことの現れではないでしょうか。」

「ICUの卒業生の中には、国際・国連NGOなど、国際公務員が数多くみられます。学生の内から、その視点を持っていること、そしてそういった話題に対して確固たる自身の考えを持ち、発信し、議論し、自分の思考を広げ、深めていく姿勢は、純粋に賞賛に値すると思います」(竹内理事長)。
着目したいのは、ICUというコミュニティにとって国際性やグローバリゼーション、SDGsといった観点は、「当たり前のもの」であること。故に、自身の殻に閉じこまらず、オープンマインドをもって広く世界に視野を広げる学生が多い。そうした学生が集い、互いに切磋琢磨することにより、普遍的な価値を見極める力が養われているのだ。
[あとがき]
改めて「異端」について――。
ICUの広報媒体において「人生を変える出会い」と言う表現が用いられるが、決して大げさではない。「心理的安全性」が担保され、あらゆる学生が安心して「異見」を交し合い「対話」を行えるカルチャーとコミュニティに浸る時間は、人生を変えうる経験となり、さらにその深みは「真善美」までたどり着くのだ。
誰も予測していない変容が、スピード感を持って訪れる現代において、時代をサバイブするための力をいかに養うか。答えは、正にリベラルアーツの真髄である「コミュニティ」と「真善美(人間力の涵養)」の2つになるであろう。
一方で、今や「異端」は人間だけではなく、動物や自然環境、AIもなり得ると言える。未来に起こりえる紛争や感染症、さらにはシンギュラリティといった未曽有の困難に対峙した際に、ICUが涵養する人間力は、その真価が問われるのだ。
そうした時には、今回の対談では言及に至らなかったICUの軸、キリスト教の精神にもぜひ立ち戻りたい。宗教における「異端」の捉え方は、今回の対談における概念とは差異はあるが、宗教の歴史において負の側面があることは知られた通りである。一方で、現代において、負の側面は徐々に自覚されることとなり、対話・連携を進める機運もある。まだ見ぬ「異端」と対峙する際に、過去に学ぶことも有益であろう。あらゆる隣人も、出会いの瞬間は異端であったのだから。
関連情報はこちら
Sub Dialogue

“知”が交わる対話録
「異端」の二人が、語らう日本への想い
実は、対談中に二人が同じ幼稚園に通っていたことが発覚。共通項も多い二人が語らった話の中で、本編に掲載しきれなかった内容を一部紹介する。
- 竹内理事長
- 私は多くの海外経験や異文化の中で育ちました。同じようなバックグラウンドを持つ学生たちには、「ルーツはひとつに決めることが大事だ」と伝えています。それによって、自分の中に確固たる基盤ができるからです。私の場合、ルーツは日本。そのため、日本の将来については責任を持って「真善美」に基づいてより良い明日へと、働きかけていこうと思っています。
- 平井氏
- 強く共感しました。私も日本に愛着を持っているからこそ、子どもの貧困問題の解決に貢献したいと考えています。国内では、7人に一人の子どもが相対的貧困で苦しんでいる現状があります。OECD加盟国の中でも低く、就学援助率も低い。この現状を放っておいて良いとは思えないし、思いたくない。何らかのアクションを起こさないといけないと思い、2021年に「一般社団法人プロジェクト希望」を立ち上げ、子どもの支援活動を行う団体へのファンディングや、私自身が次世代を担う子どもたちと語り合う場をつくっています。
- 竹内理事長
- この平井さんの考えや行動は、ICUの献学当時の思想にもつながります。献学時の文章には、「経済的な理由で学生を拒否することはない」と明記されています。当時は、データでみると奨学金をもらっていた学生は約25%。4人に一人が、奨学金を活用してICUで学んでいたことになります。それが今では、奨学金を活用している学生は当時の3分の1ほどに減少しています。もしも経済的な理由でICUへの進学を諦めてしまう学生がいたら、改善しなければいけません。
- 平井氏
- そうですね。プロジェクト希望の活動では、一人でも多くの子どもたちに感動体験を提供し、それを糧に成長してほしいと思っています。以前、プロジェクトの一環として子どもたちにICUのキャンパスを案内しようとしたことがありました。教室だけではなく、小道や広場にまであふれる音楽やダンス、さまざまな分野の「知」に触れ、生き生きと学ぶ学生の姿を見てほしいと思ったのです。
- 竹内理事長
- この話を打診された際には、即答で「喜んで!」とお伝えし、お受けしましたね。リベラルアーツの学び場として、その代表例に挙げていただけることを心から嬉しく思っています。最終的に実現はまだできていないのですが、その際にはぜひ、子どもたちと一緒にスキーに行って、交流したいですね。
PROFILE

平井 一夫 〔ソニーグループ シニアアドバイザー/プロジェクト希望 代表理事〕
ソニーグループ シニアアドバイザー/プロジェクト希望 代表理事。1984年に国際基督教大学教養学部卒業、CBS・ソニー入社。2006年ソニー・コンピュータエンタテインメント社長、2012年ソニー社長兼CEO、2018年会長。2019年よりソニーグループ株式会社シニアアドバイザー、一般社団法人プロジェクト希望代表理事。

竹内 弘高 理事長
国際基督教大学理事長。専門は経営学。1969年に国際基督教大学教養学部卒業。1976年よりハーバード大学経営大学院(ハーバード・ビジネス・スクール)で講師を務め、現在も同校で教授として教鞭を執る。2019年6月より現職。