
2023年4月に献学70周年を迎えたICU。
と2025年に創立150周年を迎える
同志社大学。
ICU 岩切学長と同志社大学 植木学長が
両大の共有する学びの本質的について対話した。
#未完の大学 #知の共同体 #オルタナティブ #アンコンシャス・バイアス
※同志社大学アーモスト館にて対談を実施
激変する時代の中で高等教育における
「学びの質」が現在(いま)問われている。
世界的にコロナ禍の行動制限が緩和され、リアルな交流の評価が再認識されつつある。
一方、生成系AIの「ChatGPT」をはじめとするAI・DX分野の発展の中、大学教育・研究機関など、あらゆる組織で加速度的に対応が進む。
昨年献学70周年を迎えたICU、また来年創立150周年となる同志社大学両大学はともにキリスト教主義教育を理念とし、それぞれ独自の発展を遂げながら、
その言葉は違えども、国際性を持つ大学として、自由な学び(リベラルアーツ教育)を提供している。
時代に迎合するのではなく、独自の文化を育み変革し続ける理念の本質とは何か。
「『明日の大学』とは、人間が過ごしている『今日』とは別の次元にある大学を指す」
という岩切学長の言葉がある。
学長就任から共にコロナ禍における大学運営を担ってきた岩切学長と植木学長。
両者の対話を通じて、大学や学問そのものが持つ普遍的価値を捉えながら、
これからの時代にこそ求められるリベラルアーツ教育の真価に迫る。
Paragraph 01
「共通善」「良心」という精神の元、
時代を超えて「知の共同体」を維持し続ける。
「学問への使命」「キリスト教への使命」「国際性への使命」を掲げるICUと「キリスト教主義」「自由主義」「国際主義」を教育理念とする同志社大学には共通する基盤がある。こうした両大学の理念は分断と対立が加速する現代社会でますます重要になっている。「ICUは2021~2025年度の中期計画において、『common good(共通善)』という概念を掲げました。これは皆にとって善いものを自由で平等な関係の中で追い求め、シェアしていくという考え方を指します。その実現の鍵を握っているのが、さまざまな知識の交流の場となる『知の共同体』です」。岩切学長が語る。
「知の共同体」について、その価値が問われたのは2020年初頭のパンデミックだ。両学長とも学長就任と同タイミングで新型コロナウイルス感染症への対応に追われ、対面授業やキャンパスにおける諸活動の制限から大学運営に苦慮した。
ICUにおける象徴的なエピソードは、学生による学費の一部返還を求める署名運動であろう。「支払った学費に対して対等な授業を受ける権利がある」などの声があがり、岩切学長から全学生にメールを送付することで対応した。「対話」を重視し、公平性のあり方について問いかける内容は、当時多くの人の目に止まり、新型コロナ禍における大学教育のあり方について考え直す機会となった。

植木学長は当時をこう振り返る。「岩切学長が全学生に送付されたメッセージには強く感銘を受けました。一方で、大学が企業のように対価に見合ったサービスを提供する存在だと一部に認識されていることは難しい問題だと感じました。大学とは本来、一方通行の教育を行うのではなく、全ての構成員がお互いに成長し合う場であるはず。その意味で、過去の世代とのつながりが刻まれた施設を維持することも欠かせません。現在自分が支払っている対価と利益だけでなく、大学という共同体の維持の重要性に学生の皆様も関わっていることに目を向けてほしいですね」。
岩切学長は同意しながらこう続ける。「今だけの合理性にこだわるのではなく、歴史を経て築き上げられたものの普遍的な価値を知るのが大切ですよね。大学の意義についてはもちろん、教育や研究に取り組む上でも、時代を俯瞰的に捉える視点は不可欠だと思います」。
Paragraph 02
両大学の「教育の質」の保証とは。
規模や取り組みの内容に差異がある一方で、「common good」や「良心」といった精神をシェアする『知の共同体』の重視は、両大学の共通項だ。その特性について深堀りをすべく、「教育の質」の観点から両大学をさらに読み解きたい。
献学以来、不断の改革を続けてきたICUにおける教育の特色は、全学生数が3000人弱という少人数制で実践される1学部1学科制のリベラルアーツならではの学際性がある。「2023年度から一般教育科目として『特別講義:リベラルアーツから問うポストヒューマン論争』を設置しました。この科目では、国際関係学、心理学、文学、物理学を担当する4人の教員が1つの教室に揃い、多様な視点から『人間とは何か』をディスカッションします。もともとは高大接続プログラムの一環として高校生向けに実施していたプログラムですが、ICU生の学際的な思考を養う場としてさらに発展させました」。ICUの一般教育科目は上限150名という定員が設けられている。「多分野の教員と学生が対話することで得られる、思いがけない発見に期待したいですね」(岩切学長)。

植木学長は今後の展開について語る。「学生が専門分野にとらわれず文理横断的に学習できるよう、さまざまな科目を体系化して紹介する試みを始めています。また、2023年秋には全学共通教養教育科目として『同志社の良心とダイバーシティ』を開講。各分野の教員が全15回の講義をリレー形式で担当し、ダイバーシティの総論から性の多様性、ジェンダー平等、多文化共生、障がい者支援の各論まで網羅的に教えます。オンデマンド科目ということもあってか、履修登録者はかなりの人数となりました。学生の皆さんが幅広い分野に関心を持てるよう、今後も学びの仕組みや発信方法を工夫していきたいと考えています」。
学際的、もしくは分野横断的な学びを展開する点は、ICUと同志社大学で共通だ。しかし、そのあり方には学生数や学部学科の構成など、大規模総合大学とスモール・リベラルアーツ・カレッジの両大学の特性が色濃く表れている。
岩切学長はICUの教育をこのように分析する。「ICUは教養学部アーツ・サイエンス学科のみ。規模が小さいため、機動的に教育を変化させられる点が大きな魅力だと思います。我々が教育を行う上で重視するのは、学生があらゆる分野に通じる問いの立て方や答えに迫る手法を身につけること。学生は入学後2年間にわたって多様な学問に触れ、2年次の終わりにメジャーを選択するという"Later Specialization"のプロセスを踏んで、自らの興味関心について理解を深めます。幅広い分野にまたがるリベラルアーツを素地に自分が選んだテーマを深く研究し、らに専門分野を広く深く学びたい学生は大学院に進学できる。一人一人の成長や志向に即しながら、理想とする学びを実現できるよう、大学にも多様性があって良いと思いますね」。
一方、植木学長も「多様な分野でそれぞれの専門性を高めていく環境は、総合大学である同志社ならではの強みだと思います。その一方、専門分野に没頭するあまり視野が狭くなってしまうことに、危惧の念も抱きます。本学は基本的に他の学部や研究科の授業も履修できるのですが、多くの学生は所属学部・研究科のシラバスしか見ていないのが現状です。こうした状況に鑑みて、まず大学院で取り組み始めたのが、開講科目を紹介する冊子の作成。有志の先生の協力の下、紙面にはいくつかの科目の概要や他研究科の学生が履修するために必要な知識について記載しました。最初はわざわざ冊子を作る必要があるのか疑問視する声もあったのですが、学生からは『冊子を見て他の研究科の授業を履修することにした』と嬉しい報告が届いています。学生や教職員の皆さんに教育・研究資源を活用してもらうために、今後も学内への発信活動に力を注いでいきたいですね」と、語っている。
「ICUのコアに迫るふたりのDialogue #03」における紐解きの通り、リベラルアーツ教育を実現する「リベラルアーツ・カレッジ」のICUと、複数学部で構成され専門的な教育を展開する「ユニバーシティ」の特性が大きく見える同志社大学。いずれも、リベラルに、自由な学びを目指す理念は創立以来変わらない。
Paragraph 03
「リベラルアーツ教育」学びの中で「想像力」と「耐える力」を涵養する
巧みに設計された「知の相乗効果」。
それが、個人と個人の狭間を埋め、共感を創出する。
大学として大規模、小規模の違いはあるものの、両大学が持つ教育の共通要素は、「知の相乗効果」であろう。ICUは少人数のリベラルアーツ・カレッジとして、31の専修分野(メジャー)を学生自身が自由に組み合わせて学ぶという分野横断型の高度な教育プログラムを提供しているが、実際には学生の主体性が不在であれば、良質な「対話」や「ディスカッション」は生まれない。また、14学部34学科を擁する総合大学という形の中で、横断的な自由(Liberal)な学びを志向する同志社大学においても学生自身の学ぼうとする主体性が問われるのは同様である。
重要になるのが、異なる知見を持つ他者が交流をし、互いに刺激を与え合いながらさらなる研鑽を促す「知の相乗効果」であり、学生の心の動きや知的好奇心の領域に踏み込む必要がある。つまり教育やプログラムに留まらず、それらが担保する「経験」のデザインを視野に入れなければならない。この「経験」という点においても両大学がリベラルアーツを実践しようとする姿勢が強くみられる。このパラグラフでは、既に両大学において展開される好事例を題材に「知の相乗効果」の重要性について紐解く。
ICUでは、2023年4月にトロイヤー記念アーツ・サイエンス館が開館し、多くの学生が活用している。その名称の通り、アーツとサイエンスの出会い、「知の融合」をコンセプトとした建物である。建物内には、全学生が利用する5つの大教室や、人文・社会科学系の研究所、自然科学系の研究室と実験室が設けられ、全面ガラス張りの実験室とすることで、他分野をメジャーとする学生が自然科学の学びに触れられるシナジー効果を狙った。「他の学生がどんな学問を学んでいるのか、日常的に意識できる仕組みを作りたかったんです。教室や学生寮も同様で、多様な分野を専攻する学生が集まることで、相手を知るために対話をしなければならない状況を生み出しています。同じ専門分野を多くの学生が学んでいる場合、こうした対話は生まれにくいのではないでしょうか。異なる文化や価値観と向き合いながら対話を重ねていく態度は、グローバル化が進む社会でも重要だと思います」(岩切学長)。
同志社大学でも多分野の教員を巻き込む新たな取り組みが始まっている。ポストコロナ社会への対応をテーマとする「ALL DOSHISHA Research Model COVID-19 Research Project」を2020年に発足。教員から応募があった77の研究課題に対して、シンポジウムの開催や研究費の支援などを行った。現在は新たに「All Doshisha Research Model 2025」を立ち上げ、2022年度から3年間にわたってSDGs達成につながる研究課題への支援を行うことを発表している。植木学長は活動の成果をこう語る。「シンポジウムなどで各分野の教員が意見を交換した結果、共同研究に取り組む気運が高まったと感じます。学生はもちろん、異なる分野を専門とする教員同士の交流を創出すべく、エンカレッジすることも大切ですね」。

先進国の中で取組みが遅れているとされる日本においても、性や働き方、生き方などの「多様性」の重視が徐々に広がりつつある。一方、一般的には多様な価値観が存在するが故に、個人間の「共感」が持ちづらい社会に変容しているとも言えるであろう。いかに学ばせ、相互作用・共感を促し、さらには失敗の経験を与えるか。やはりそのような「大学が主導する『経験のデザイン』」が、未来社会を生き抜く力を養う上で、益々重要となるであろう。
「共感」に関して、植木学長の興味深い発言をご紹介したい。「ブレイディみかこ氏のエッセイ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社,2019)で紹介されていたのが、シンパシー(Sympathy)とエンパシー(Empathy)という言葉。どちらも『共感』と訳されることが多いのですが、シンパシーは気の毒な立場の人や問題を抱えている人、自分と意見が似ている人に対する感情的な共感を指します。片やエンパシーは、かわいそうだと思えない立場の人、自分と異なる理念や信念を持つ人の考えを想像する力です。多様性を尊重するにはシンパシーだけでは足りず、知的な作業としてのエンパシーが求められます。大学という高等教育機関で育むべきなのは、まさにこのエンパシーではないでしょうか」。
岩切学長も同意しながらこのように続けた。「ICUのクリティカル・シンキングにも通じる言葉です。自身や他者の意見をそのまま信じ込むのではなく、多方面から検討を重ね、議論を発展させていく姿勢が、今後ますます重要になると思います」。さらに、感覚と知性の両方を働かせることの大切さは、フランスの古典文学からも読み取れると続ける。「マルセル・プルーストの小説『失われた時を求めて』には、主人公の少年が紅茶に浸したマドレーヌを口にした途端、昔の記憶が鮮やかによみがえるシーンが描かれています。記憶の糸口となったのは感覚ですが、そこから失われた時間を見いだすためには、知性による分析が必要でした。感覚と知性の両輪があってようやく、真実に迫ることができるのです」。
ICU名誉教授北原和夫氏は、「リベラルアーツとは偏見や先入観から解き放たれ、自分の頭で自由に考えるための『技』」であると語る(「ICUのコアに迫るふたりのDialogue #05」)。クリティカル・シンキングはリベラルアーツを支える思考法であり、この思考がエンパシーを育てる。まさに知の相乗効果の鍵である。固定観念や常識に囚われない、このリベラル(自由)であることが改革の実践や継続を可能とする。
Paragraph 04
変化の濁流を乗り切るために必要なのは、
「今日」ではない次元のオルタナティブな姿勢。
パンデミック以降、大規模かつ急速な社会変化が巻き起こる現代。中でも近年注目されるのが、2022年の末よりさまざまな業界で取り沙汰されている「ChatGPT」等の生成系AIだ。専門家からは誤情報の拡散や情報漏洩のリスク、サイバー攻撃に対する脆弱性など、数々の問題点が指摘されている。
教育業界も例にもれず、生成系AIへの対応を迫られている。特に学生が生成系AIを使用してレポートや論文を作成した場合、十分な学習効果が得られないと懸念する声は大きい。各大学は相次いで学生や教職員に対して生成系AIの利用や成績評価に関する指針を発表。2023年7月には、文部科学省が各大学の指針や有識者の見解をまとめた「大学・高専における生成AIの教学面の取扱いについて」を発出した。
「生成系AIの出現によって、『人格』の重要性がより高まりました。生成系AIには感情や経験がなく、人間同士で行うような思慮深い対話は望めません。ICUにはアーツ・サイエンス学科がありますが、キリスト教の精神に立ち返ると、ArtsとScienceに加えて、時代を超越するようなWisdom(叡智)が必要と言えるでしょう。この3つの要素がそろうことで、人間や大学に対する深い思索ができるのだと思います」(岩切学長)。
植木学長も「試験やレポートに生成系AIを使用することが差し迫った問題として取り上げられますが、私は今こそ本質的な問いに立ち返るべきだと感じます。大学で学生が学ぶべきことは何なのか、教職員は学習成果をどうやって把握するのか……。同志社大学の徽章はクローバーを思わせる3つの正三角形で構成されているのですが、これは『知育・徳育・体育』の全人格的な調和を目指す本学の教育理念を象徴したもの。中でも徳育においては、生成系AIに回答させるのではなく、自分自身で考え抜くことが欠かせません。『良心』『共通善』といった倫理的な視点に立てば、自ずと選ぶべき道が見えてくるのではないでしょうか」と語る。
両学長の言葉から、時代の潮流を捉えながら現状の教育のあり方に満足せず、変容していく大学の姿勢が浮かび上がる。

ICUにとっての改革の姿勢は、「明日の大学」という言葉がすべてを表している。「『明日』とはカレンダー上の日付ではなく、『今日』ではない次元を指し示すメタファー(隠喩)でしょう。時代ごとの価値観をそのまま反映するのではなく、人間の時間とは異なる次元に大学を置き、未知なるものへと開かれた学びを提供していく。そういった意味で、ICUは『永遠に未完の大学』なのです」(岩切学長)。
新島襄が大学の完成には200年かかると語っているように「本学も今でも発展途上の大学として、新しい学位プログラムの設置、先端的教育・研究体制の整備などに積極的に取り組んでいます。一方で、教育効果が表れるまでは長い時間がかかります。社会変化に即座に対応するだけでなく、創立者の理念を受け継いでいくことも欠かせません。原点に立ち返りながら、時代とともに変えるべき部分を見定めていく。その過程を繰り返すことが重要であり、大学が『完成』することはないのだと思います」(植木学長)
献学70周年を迎えたICUと創立150周年を迎える同志社大学。両大学はそれぞれ大学としての発展、規模は異なる。しかし、リベラルアーツ的視点と学修者本位の教育がそのコア(深層部分)における共通点であろう。現代社会において、紛争、経済環境や個別の家庭環境など、さまざまな状況下におかれながらも、学びを諦めない人々がいる。知を共有する大学の「オルタナティブ(alternative)な姿勢」の重要性がさらに高まる中、「未完の大学」として、不断の改革の姿勢を持ち続ける2大学。そこには、自由に学び続ける大学という場を守り、発展させたいという想いが息づいている。
Paragraph 05
あらゆる大学の基盤にある「世界通用性」。
その質を最大限高める独自のカルチャーの重要性
近年、日本の多くの大学において「インターナショナル」、「グローバル」を冠する教育プログラムが発展してきた。日本から世界に目を向けるという視点での教育である。しかしながら、ICUが70年間にわたり実践してきたのは「世界通用性」を持つリベラルアーツ教育。日本に位置する世界の大学の1つとして、教育プログラムをはじめシラバス、GPA制度、科目のナンバリングなど、あらゆる教育システムを世界基準とするものだ。このパートでは「世界通用性」という観点から、両大学の展望を語ってもらった。
「そもそも、大学というのは世界共通です」と岩切学長は切り出す。「各大学で施設や設備、在籍する研究者は違いますが、教えている内容は大きく変わりません。大学を設置するとはすなわち、世界各国の大学が共有する知識や方法論の枠組みに加わること。この前提に立てば、『全ての大学は世界通用性の上に立っている』と言えるのではないでしょうか」。
岩切学長の言葉に共感を示しつつ、植木学長はこう続ける。「あらゆる学問の目的は真理を探究することにあります。分野ごとに対象は違っても、問いを立て、答えにたどり着くために考えるという方法は変わりません。例えば、幾何学の証明問題を解くとき、補助線を引くことで新たな局面が見えたという人は多いのではないでしょうか。こうした発想は、あらゆる学問分野で応用できるはずです」。
日本では長らく学問分野が文系・理系に大別され、グローバルスタンダードとの相違の観点で近年はその断絶の深さが問題視されている。岩切学長は現状を批判的に捉え、学びの根本に立ち返るべきだと主張する。「 “Science”は理系の学問を指す言葉として使われていますが、その語源はラテン語で『知る』という意味の“socio”にあります。分野を問わず、『知りたい』という気持ちが “Science”の基本です。現在の教育システムでは文系・理系に区別されていますが、学問の根本にあるのは知の好奇心だということを認識したいですね」。
「同志社では、大学院生と企業の若手社員の方々が一緒に学び、未来社会で求められる技術や製品を構想する授業を行っています。学生にとってはアイディアを現実化する方法を学ぶ良い機会になりますし、社会人の皆さんからも学生のユニークな発想に刺激を受けていると好評をいただいています。大学として、学生が自由に発想できる場を提供することがとても大切なのだと改めて実感しましたね」(植木学長)。
「自分の意見を誰かに捻じ曲げられたり制限されたりしない、自由な対話の場を保障するのが、大学という教育機関の役割だと思います」と岩切学長は続ける。

ICUと同志社大学の双方が持っている個性、学生の自主性を重んじる自由(Liberal)な学風は既存の枠を超えて自由に学ぶということ。それは大学の持つ知が大学内にとどまることなく、社会に、世界へと繋がっていくものである。両大学ともに、学生や教職員の間に大きな壁はなく、「真に自由(Liberal)」なカルチャーが存在する。そうした文化が根付くコミュニティがあるからこそ、学生たちの「心理的安全性」が担保でき、豊かな「対話」の促進、失敗も辞さない「経験」が実現できる。こうした人生を生き抜く上で大切な糧を学ぶ「好循環」を生み出すことが、引いては学生一人ひとりの「世界通用性」の涵養につながるのだろう。
[あとがき]
「アンコンシャス・バイアスとの戦い」――。
近年よく取り上げられる「ダイバーシティ」と「インクルーシブネス」。ダイバーシティやインクルーシブネスの実践を考える際に、課題として挙がるのが「アンコンシャス・バイアス(Unconscious bias:無意識の偏見)」だ。
アンコンシャス・バイアスは常に我々の前に立ちはだかっている。どのようにこの問題を乗り越えていけばよいのだろうか。リベラルな大学としてあり続ける両学長の言葉にヒントを探してみた。
「これまで国際化というと、共通言語として英語を使用することが重視されてきました。その実践としてICUが取り組んでいるのが、日英バイリンガル教育です。母語に加えて別の言語を習得するという学びは、世界中の多くの人々の言語の構造を理解するのに役立つはずです。言葉の世界通用性とともに言、語において国や地域、個人が持っている特殊性や個別性に目を向けることはとても大切だと感じます」(岩切学長)。
「タイムパフォーマンスという言葉の流行に見られるように、昨今は短い時間で最大限の効果を得ようという風潮が高まっています。しかし、そういった効率重視の考え方と大学教育とは本来相いれないもの。長い時間をかけて、結果が分からない課題に取り組んだり、失敗を経験したりすることで、貴重な学びを得ることができます。学生の皆さんにそうした体験の価値を伝えるために、大学側も変化していかなければなりません」(植木学長)。
言語を通して世界で個として自立すること、体験を通して内なる自分を解放すること。外と内、方向は違えど、この2大学は「未完の大学」として自由な学びを追究し続けている。その学びのしくみにこそ、アンコンシャス・バイアスから解き放たれる手がかりがあるのではないだろうか。
先行き不透明なVUCA時代において、何を変化させ、何を固持すべきか。過去から現在、未来までを捉えて大学の舵を切ろうとする、両学長の「慧眼」。さらには、常に「意識的に」改革を試みる姿勢。
未来社会を生き抜くすべての若者のために、持続可能な社会や教育を実現する鍵は、今を担う人物の「姿勢」に託されている。
関連情報はこちら
「ICUキャンパスツアー動画:
ICUへようこそ」
「自分を、世界を発見する
― ICU教養学部生4名の学び」
「トロイヤー記念アーツ・サイエンス館で
「出会う」3つのストーリー」
― 当対談のダイジェスト動画はこちら ―
Sub Dialogue

“知”が交わる対話録
五感を駆使して「本物」に触れる学び
コロナ禍を受けてICTの活用が進む一方、二人の対話では「本物」に触れる学びの意義が取り上げられた。対談が行われた京都を主題に、五感を刺激する学びの可能性をひもとく。
- 岩切学長
- 京都は町全体が文化都市ですよね。日常生活を送りながらさまざまな文化に触れられる環境が素晴らしいと思います。実は対談前日には、『源氏物語』の「宇治十帖」で舞台となった宇治市を訪れました。残念なことに源氏物語ミュージアムは休館日だったのですが、宇治神社の周辺で「早蕨(宇治十帖の第四帖)」にちなんだ古跡を見かけたのはうれしかったです。物語内に登場した場所や景色を体感すると、読むだけでは得られない、より深い親近感が得られますよね。
- 植木学長
- おっしゃる通りですね。本学に着任してから、祇園祭の季節に学生が浴衣で授業を受ける様子を見て、驚くとともにほほえましく感じたことを覚えています。コロナ禍でICTの活用が進み、遠隔授業も難なく実施できるようになりましたが、それでは視覚と聴覚しか使いません。実際にその土地を訪れたり現物に触れたりして、触覚や嗅覚、味覚をフルに活用して学ぶことの意義を強く感じます。
- 岩切学長
- 私が今後のキーワードだと感じているのが、美術用語の「マチエール」です。これは「絵画の絵肌や彫刻の質感など、作品における材質がもたらす効果」を指します。8Kの超高精細なディスプレイで映し出したとしても、作家の筆致や絵の具の盛り上がり方、キャンパスの材質など、「マチエール」にあたる要素を体感するのは難しいでしょう。本物を見るという体験の価値は計り知れません。
- 植木学長
- とてもよく分かります。古典和歌のモチーフに、秋の末から冬の初めにかけてパラパラと通り雨のように降る「時雨」があります。私が生まれ育った関東の冬は乾燥が激しく、ほとんど雨が降らなかったので、なかなかその情景を思い浮かべられませんでした。ですが、京都に引っ越してから秋から冬にかけて頻繁に雨が降り、「あ、これか!」と感激したことを覚えています。時雨によって木々の葉が色づくという和歌の類型も、これまで以上に実感を込めて解説できるようになりました。学生の皆さんにも、学びを体感する機会を提供していきたいですね。
PROFILE

岩切 正一郎 学長
国際基督教大学学長。専門はフランス文学。2008年には第15回湯浅芳子賞(翻訳・脚本部門)を受賞。パリ第7大学テクスト・資料科学科第三課程修了 (DEA)。国際基督教大学アドミッション・センター長、教養学部長を経て2020年4月より現職。

植木 朝子 同志社大学 学長
同志社大学文学部国文学科教授。博士(人文科学)(お茶の水女子大学)。専門は中世歌謡・芸能。お茶の水女子大学助手、十文字学園女子大学助教授などを経て、2005年に同志社大学文学部国文学科助教授。2007年より同教授。文学部長・文学研究科長、副学長、教育支援機構長を歴任し、2020年4月より現職。

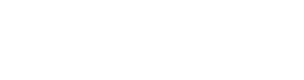

![岩切 正一郎[ICU学長]× 植木 朝子[同志社大学学長]](/knowledge/dialogue/img/dialogue09_name.png)