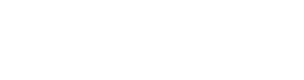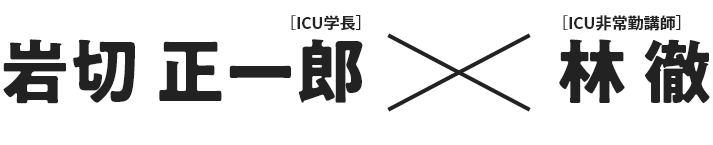ICU非常勤講師の林徹氏は、
日本とポリネシアの先史考古学の専門家。
ICU同窓生でもあり、遺跡の上で学ぶ日々を通し
考古学への思いを強くしたという。
そこにあるリベラルアーツの醍醐味を
岩切学長との対話を通して
掘り起こしていく。
#考古学 #リベラルアーツ #遺跡 #時間軸
縄文文化の上に拡がる深化する「学びの庭」。
考古学のリベラルアーツ的醍醐味とは――
今回の記事は、「考古学という学問」にスポットを当てる特別編である。
これもまたリベラルアーツのひとつの側面でありICUの姿としてお楽しみいただきたい
ICU は62 万㎡の敷地に学生寮や教員住宅という40棟余りの建物が点在し、キャンパス内の広大な自然とともにICUの重要なアイデンティティの一部となっている。これらは歴史を重ねながらもインフラ整備、研究・教育の要求に応えるために拡充されてきた。現在は基本計画「キャンパス・グランド・デザイン」に基づく整備が進んでおり、中でも2023年から授業に使われる新館「トロイヤー記念アーツ・サイエンス館」は、アーツとサイエンスの融合、学問分野を超えた知の統合を実現する場として、学内外の期待を集めている。
旧石器時代から続くこの土地での営みの上に、ICUの学びがある。まさにアーツとサイエンスの融合したキャンパスだといえるだろう。このキャンパスを利用した考古学の授業は、献学間もない1957年にはすでに始められた。授業は「学内での発掘という実習を含む点が大きな特徴で、現在も受け継がれている。
ICUのキャンパスは、武蔵野台地南縁を流れる野川に沿い、国分寺崖線という崖の上の高台に位置する。水源、日当たりや風通し、見晴らしにも恵まれた地形は10万年ほど前に形づくられた。人々の営みは旧石器時代にも遡ることができ、縄文時代には集落が営まれた。 こうした遺跡を包摂するICUのキャンパスで考古学を学ぶ意味を考えてみる。
トロイヤー記念アーツ・サイエンス館
初代学務副学長の名前を冠するこの建物は、自然科学系の分野に限らず人文・社会科学系の分野との融合を図ることでリベラルアーツをさらに進化させ、「明日の大学」にふさわしい学びを目指したもの。対話を重視し、人と人とのつながりやシナジーを生み出す場であり、環境面でも最先端の工夫を凝らした建物となる。
新館には、考古学研究室が入り、またキャンパスの「地層」を切り取ったモデルが展示されるなど、考古学はリベラルアーツの文理融合の象徴のひとつとして表現される予定だ。
Paragraph 01
考古学とは、総合的な人間研究だ
ICU構内では現在43カ所の地点で遺跡が調査されている。その長年の発掘調査の成果は現在学内の「湯浅八郎記念館」で見ることができ、その展示物は圧巻だ。しかし「これでも調査できているのはおそらく1%程度だろう」と、考古学の教鞭をとる林講師は語る。
林講師によれば「大学の敷地内に遺跡がある例は稀で、特に縄文の大きな集落などの遺跡がある大学は他にまずない」とのこと。ましてや学生達が自らのキャンパス内の発掘調査に関われる学びは他にほとんど類を見ないだろう。
考古学を学ぶ上で、この環境はどんな意味を持つのだろうか。
岩切学長はこの対談に先だち発掘した土器に触れる機会があったという。「土器を触る体験は思った以上に新鮮でした。写真や博物館の展示を見るだけではなくて、手に持って感触や重さを確かめられるというのは、リアリティがまったく異なる。他の学問の文献研究とは異なり、考古学では物は出ても文献はない。土器の欠片に対しても想像力を使う部分と、科学を使って分析する部分があり、極めて複合的です」。
その一連の学びを、ICUならばキャンパス内で学べる。机上の検証だけでなく肌で感じ、縄文人に思いをはせる。「こうした複合的なアプローチはリベラルアーツそのものですよね」。そう岩切学長が示すところから対話は始まった。

「そうですね。複合的であることはもともと当然なのです。一般的に考古学というと、遺跡を発掘して出てきた土器などを細かく研究していく学問だと思われがちです。しかし、それはあくまでも手段で、目的はその道具を作って使って暮らしていた[人間の研究]にこそあるのだと考えます。どういう人たちが、何をどういう理由で作り、どんな暮らしをしていて、その結果どうなっていったか、というところが知りたい。つまり考古学とは過去に限定した総合的な人間研究なのです」(林講師)。
考古学は本来、分野横断的・統合的なリベラルアーツの学びに他ならないと林講師は解説してくれた。「考古学は考古学だけでは成立しません。土器ひとつをとっても、その物質的・機能的な側面もあれば、文化的・社会的な価値もある。健康や食、心理なども関わってくる。[物]を対象とした実証的な側面とともに、解釈の部分が非常に難しい。理論考古学や認知考古学というジャンルもあり、解釈を担う学問が開拓されているところです」(林講師)。
岩切学長から「何か具体的な例があったら教えてもらえますか」との質問が出た。
「そうですね。例えば、石器を作る時に出た石の欠片が散らばったままの状態で残されている、そんな遺跡が出てくることがあります。この散らばったパターンを調べると、作った場所、位置、向きに加え、右手と左手をどう使い分けていたのかなど、分布状況からある程度判断ができるわけです。そこから類推できることは多岐にわたりますよね」。一説によると人類は太古から右利きの比率が高いという。そうした他の研究とも照らし合わせて、どう解釈するのか。問いを立て、検証していく。それが重要だという。
Paragraph 02
縄文文化から弥生文化へ
「また、遺跡を通した人間研究には、時間軸に着目する視点も欠かせません」と林講師は続ける。「石器を作った場所には土が積もっていくのですが、発掘していると、時を超えてずっと後の時代にも同じところで石器を作っている場所が見つかることもある。これはきっと百年千年と時が経つ間に残された石器の一部が少し浮いて、後の時代の人に発見され、ここは石器を作っていた場所だったとわかって、そこがまた石器を作る場所になった、そんな結果だろうと考えています。私は[場の意識]と呼んでいるのですが、人間とはそういう[場の意識]や場の持つ特性を無意識に感じ取っているのかもしれません」。
時間軸で世界と並べて比較すると見えてくることも多いという。「世界ではとっくに農耕を始めている時代でも、日本ではまだ縄文時代が続いていてずっと狩猟採集を続けていた。この理由をいろいろな証拠から考えていくと、どうも農耕する必要がなかったようです。日本の縄文時代は、四季があり降雨量や湿度という水の環境がよく、生態系が豊かで多様性があり、人間にとって非常に生きやすい環境だった。そのため縄文人は急いで農耕に進む必要がなかったと考えられています。もっとも、最終的には気候が寒くなり農耕に進むわけですが、世界から見ると実に何千年も遅れたわけです」(林講師)。

「それは面白いですね。農耕は人間にとっては作業であり労働ですよね。農耕を始めるのは遅くなったけど自然に恵まれた、そのおかげで縄文時代は大らかさがある、すごく面白い文化ですし、後の私たちの気質にも影響があったかもしれない。そういう点も研究しがいがありそうですね」(岩切学長)。
「そうですね、大らかだったように思います。ただ狩猟採集も調べていくとイメージしているより働いていたようです。縄文人は栽培などさまざま工夫をしています。例えば花粉分析で最近分かってきたのは、美味しくて栄養価も高く主食にもなる栗を作るために、他の木を切り倒して栗林を作っていた。ですから、ただのんびりしていたわけではなく、労働を惜しまずに前向きに生きていた人達であることは確かです。イメージが変わりますか? けれども自然と共に生きていますから、天体から蟻に至るまで非常に視野が広く、身の回りのものを全部観察して、そこから学んだことを生かしている。おそらく縄文人は自然に関する膨大な知識体系を持っていたでしょう。それが弥生時代に農耕社会になると専門のノウハウが必要になるし、分業され、技術が積み重なっていき、文化を変えていく。まさに大きな転換があったと思います」(林講師)。
Paragraph 03
深化するリベラルアーツ
「もしICUの学びで言うならば、一般教育科目で幅広く学んでいくという姿勢と、メジャーで専門的なものを深めていく、その転換点のようですね。専門的になっていけばいくほど、同時に広い視野を持ち続けることが重要で、これは意識しないといけない。本来は人間が備えている可能性です。縄文時代的な生き方をしようと思えばできるし、弥生時代的な専門や分業の世界に入っても適応していける。人間の持っているいろいろな可能性の姿が、ここに大きな形で描かれているような気がします」(岩切学長)。
林講師もICUの同窓生であり、ICUのリベラルアーツを通って学びを深めた一人だ。それだけに学長の意見に賛同する点も多いようだ。「いま学長がおっしゃった『適応』というのはまさにキーワードですね。縄文的な生き方にも弥生的な生き方にも適応できるし、それは相反するものではない。私はICUの大学院では比較文化で、ルネッサンス音楽、漢文、言語学など、学ぶべき分野が多くて最初はたじろぎました。けれど実際に勉強してみるとこれは全部がつながっていく。それが面白いなと思いました。人間のやることは人間を根幹に据えると全部つながる。そこから私の考古学の見方も変わって、理論的にもいろいろなことを考えるようになりました」(林講師)。
「理解のために少々解釈を拡げてみたいのですが。あえてフロイトを持ち出して例えてみると(フロイト著「W. イエンゼン『グラディーヴァ』にみられる妄想と夢」)、考古学で地層やら古い時代の物を発掘していくということと、自分が忘れていた過去の記憶に近づくのは共通するのかもしれない、とお話を伺って感じました。掘ってみたら出てきたものを、科学と知見と想像力でもう一度繋げていく、この作業は人間の記憶の問題とも結びつきますよね。同様に、集団や社会が古くから幾層にも積み重なっていることとも結びつく。学問としてだけでなく本当に人間全体をつなぎ、捉える。そんな学問なのでしょうか」(岩切学長)。

「その通りですね。考えてみれば、我々の祖先である彼らが頑張って生きのびなかったら、我々はこの世に存在していない。意識していなくても、その命と DNA は、まさに我々に直結しています。また、考古学自体の目的は人間研究ですが、アプローチの手段は理系的です。年代測定、成分分析などの技術が進展したことで、それまで目で見えるものしか扱えなかったものが、目に見えない分析データによって、当時の環境が見えてくる。どんな植物が生えていたかなど、色々とわかってくる。サイエンスをベースに人間研究を進めると、全部がつながっていくわけです」(林講師)。
Paragraph 04
長いスパンの時間軸で考える
「もう1点、抽象的な事柄を伺いたいのですが」と岩切学長の興味は尽きない。「考古学の時間は百年千年万年という、すごく長いスパンですよね。その時間軸で個別の事、全体の事を考えていくわけですね。一方で今の我々の生きている時代は、時間が常に切迫している。常に、次々に新しいものを追い適応を求めるわけです。そんな現代に生きていると考古学の持つ時間感覚、大きい時間で対象を捉えるセンスがすごく魅力的に感じますが、林先生はどんな思いを持っていますか?」(岩切学長)。
「まさに時間の感覚が他の学問分野とは違いますね。実は考古学は過去のことを研究するわけですが、同時に現代を[千年後から見る]というような、未来から考える視点も兼ね備えるわけです。人間は基本的に目先のことばかり考えて生きています。しかし必要に応じて未来のことを考えなければいけないとなった時にどうするか。過去を材料にするしかないわけです。それが歴史学と考古学の果たす役割のひとつでもあります。過去から未来にわたって、隣り合う学問がぐるりとつながっていきます」(林講師)。
「リベラルアーツに照らしてみたとき、もうひとつ符号する点がありますね」と岩切学長。「何かにすぐ役立つスキルを追い求めるだけが学問ではない。短いスパンで見ると何に役立つかわからない事でも自分の中に入れておくことによって、長いスパンの中で意味を持ってくるものがある。あるとき、ある道筋でぐるりと全部つながっていく。その種をきちんと自分の中に播いておく。このことの価値は長い時間経ってみないとわからないので他者に伝えにくいですね。長い時間をそれなりに生きて経験を重ねた大人たちが、きちんと学生に大事だと言っておかないといけないところでしょう」(岩切学長)。

「長いスパンというのは非常に大事ですね。昔の人が自分の祖先であることにロマンを感じます。我々も自分の子孫がどうなるのかを思ったりしますよね。それを見届けることはできないけれど自分の祖先たちもそう思っていたとしたら、今その声を聞いてあげたい。コミュニケーションを取ってみたい、そういう気持ちになります。同様に将来に対してもバトンをつなげたい。[長いスパンの意識]というのは、どこまでも広げることができる。学びに関しても同じで、私も恩師のキダー先生に言われていました。『今やっている授業の内容やデータがすぐに何かの役に立つということはない。でも君たちの長い人生ではいろんな場面があって、その瞬間瞬間に授業で学んだ映像や話を、あっと思い出すことがある。それが大事なんだ』と。これは、私も学生にもっと伝えていかないといけませんね」(林講師)。
[あとがき]
本気で面白がる大人の影響力
林講師は考古学という学問を楽しんでいる人、そんな印象が強い。ご本人に伺ってみると「基本は面白がっています。学生にも『俺は面白がっているよ。面白いだろ』と伝えています」とのこと。大人が本気で面白がっていることを間近に見られる学生達は、その姿とともに熱量の大きさを見て「面白そうにしているけれど、何がそんなに面白いのか」と好奇心を募らせていくのだという。好奇心が好奇心を呼び、互いに学問を掘り下げていく。これが教育の質につながるのだろう。
また、お二人の話で印象的なのは、時間軸の捉え方だ。時間をどんなスパンで切り取って考えるかで、見える世界や意義が変わる。考古学だけでなく、リベラルアーツを考える上では複眼的な視点に加え、複時的ともいえる物差しが有用であると納得した。
関連情報はこちら
PROFILE

岩切 正一郎 学長
国際基督教大学学長。専門はフランス文学。2008年には第15回湯浅芳子賞(翻訳・脚本部門)を受賞。パリ第7大学テクスト・資料科学科第三課程修了 (DEA)。国際基督教大学アドミッション・センター長、教養学部長を経て2020年4月より現職。

林 徹 非常勤講師
国際基督教大学教養学部卒、同大学院比較文化研究科(当時)修了。
専門は先史考古学。特に日本とポリネシアの石器・漁撈文化。 環境適応の観点からイースター島の歴史解明にも取り組む。 内外各地の遺跡を発掘調査。ICUでは講義のほかに発掘実習も指導。学生の団体、美術・考古学研究会の顧問も務める。