NEWS
登大遊氏による講演会「コンピュータ技術とサイバーセキュリティにおける人材育成法および将来展望」を開催
公開日:2024年10月9日
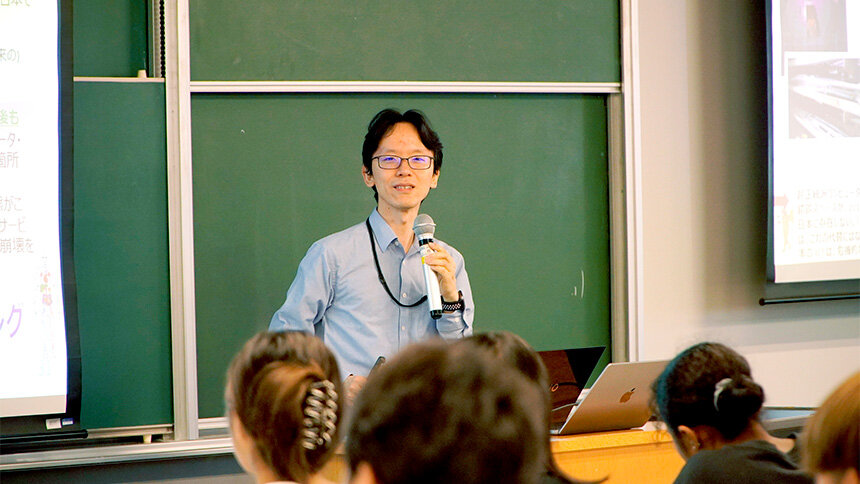
2024年10月3日、NSフォーラムが開催され、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)サイバー技術研究室長 登大遊(のぼり だいゆう)氏が「コンピュータ技術とサイバーセキュリティにおける人材育成法および将来展望」と題する講演を行いました。NSフォーラムとは、本学の自然科学デパートメントが主催するイベントで、主に学外の研究者を招き、最先端の技術や研究を紹介をしていただくセミナーです。司会は石橋圭介教授(メジャー:情報科学)が務め、会場、オンライン合わせて約100名の学生・教職員が参加しました。
登大遊氏は、VPN Gateを開発し、NTT東日本や自治体のテレワークシステムの開発をするなどの多大な功績がある、日本のプログラマーです。
講義で登氏はコンピュータの基盤を知る人材不足を解消するためには、自動車教習所のように教科書で学ぶだけでなく運転をしてみるということが重要で、そのためにも自由に試行錯誤できる「インチキ」サーバー環境をつくり、その試行錯誤を楽しむこと(サーバー構築の場を「苦行センター」と呼ぶなど)が大切だと話しました。また、このように新しい発想と価値を生み出すための組織「自由システム」と厳格な統治体制をとる組織「厳格システム」はバランスが重要で、今後、組織に両方の要素が必要だとも触れました。
くわえて、登氏は、今後は、コンピューターも通信もわかる人材が必要であることにも触れました。そして、ソフトウェア領域だけではなく、船で例えると船室であるハードウェアの構築ができる人も必要と述べました。また、構築には、情報に関する知識だけではなく、人文・社会・自然科学にまたがる知識が刺激を与えてくれると話しました。

質疑応答では、試行錯誤の場としての大学の重要性や、一見苦行のように見える0から1を作るシステム・ソフトウェア技術構築に関わる意義として、永遠に積み重なっていく技術開発に関わることができ、「人生の有限性という虚しさを打ち消してくれる精神的価値」があることなど、活発な意見交換がされました。
参加した学生からは以下のようなコメントがありました。
- 先人が積み上げてた苦行の上に自分の苦行が積まれていくことは、それが苦行だとしても価値があるものだと気付かされました。
- 今まで組織の中の一部に位置する事務職、経営職のどちらになりたいかという二極的な考え方でしかキャリアビジョンを考えていませんでした。しかし、どちらも兼ね備えていることが、新しいことを開発、そして発展させる組織を築き上げるのに必要であると気付くことができました。
- プログラムの基礎を作る人材の育成へのポジティブな姿勢だったりと、登さんが非常に楽しんで情報科学分野のことを考えているところを見て、大変刺激になりました。
- 文系の学問も織り交ぜながら、というお話が、今の自分が出来ることであり、やりたいことなのだと気付かされ、希望が持てました。
- 人類の欠乏状態が新しい技術を生んだという[話は]リベラルアーツの大学であるICUに通っている身としてとても興味深く考えさせらるものでした。
コンピュータ技術とサイバーセキュリティの第一線の技術者による、刺激に満ちた講演となりました。