NEWS
北陸先端科学大学院大学 谷池俊明教授によるNSフォーラム「カーボンニュートラル社会を目指す触媒とAIの挑戦」を開催
公開日:2025年10月22日

2025年10月16日、北陸先端科学大学院大学(JAIST)先端科学技術研究科教授 谷池俊明氏を招いてNSフォーラム「カーボンニュートラル社会を目指す触媒とAIの挑戦」がトロイヤー記念アーツ・サイエンス館で開催されました。NSフォーラムは、自然科学デパートメントが学外の研究者の最新の技術や研究を紹介するセミナーシリーズです。司会は田旺帝教授(メジャー:化学、環境研究)が務めました。ICUとJAISTは2014年から推薦入学協定を締結しているため、最後にJAISTの紹介もありました。
講義では、はじめに温暖化が与える影響とカーボンニュートラルの必要性について気候変動に関する政府間パネル(IPCC)のデータをもとに説明がありました。現状のままでは、2050年に気温は2°C高くなり、その結果、植物の多様性が16%、サンゴは99%失われるなど、農業・漁業にも深刻な影響があるとされています。気温上昇を抑えるには、物質文明の仕組みを変えなければ変わりません。
そこで、谷池氏が着目したのが化学プロセスの80%に、GDPの35%にインパクトを与えている「触媒」です。触媒は自分が変わることなく周りに影響を与えて大きな成果を導くもので、特定の化合物を生成するよう化学プロセスを導くことができます。例えば、有機EL、おむつ、ペットボトルなど日常で広く使われている高分子の生成や、原油からガソリンなどを生成する流動接触分解に触媒は欠かせません。廃棄物から物質を生成したり、CO2を排出せずに水素を生成したりできる新しい触媒が発見できれば、化石ベースの社会を変えることができると谷池氏は述べました。
しかし、流動接触分解1つとっても、分子を吸着させ、分離させ、吸収させるといった複雑な化学プロセスそれぞれに触媒が必要になるため、膨大な新しい触媒を探す必要があり、かつ触媒の反応は条件(パラメーター)によって変わるため、膨大な実験が伴います。これまでの触媒の発見は仮説をもとにした2万回もの実験(ハーバーボッシュ法発見の例)や予期せぬ発見に依拠しており、無限の可能性の中から2050年までに未知の触媒を発見し革新を起こすのには限界があります。そこで、谷池氏はAIに注目したと語りました。さまざまな元素を組み合わせて新しい触媒素材の候補をつくり、さまざまなパラメーターとかけあわせた相関関係を予測させ、適切な候補を絞っていくというものです(仮説駆動からデータ駆動への転換)。ただし、AIが予測できるようになるためには膨大な数(例えば1万点)の学習データが必要で、過去の実験データでは足りません。そのため、谷池氏のチームはデータをとるための効率的な装置(合成から評価まで人の手を借りることなく自動的にできる)をつくり、1日4,000件の実験を続けることでAIが学習できる状態にしました。また、AIで記述子(descriptor)を生成する技術を実現しました。記述子とは高次元の特性を低次元の数値で表現する方法ですが、未知の触媒の記述子が分からないためです。これらの技術を駆使した結果、谷池氏はAIが10億個の触媒素材候補から、既知の触媒約40個の3倍にもなる約120個の新しい触媒と数個のチャンピオン触媒を提案できたと述べました。
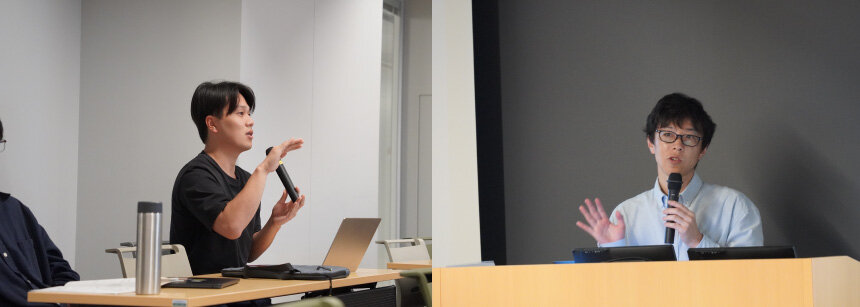
講演後の学生・教員との質疑応答では、目的変数を人間でなく今後機械で設定できるかの議論や、新しい触媒の工業化についてアカデミアとプラントが対話していく必要性などが討議されました。
参加した学生からは、機械学習やAIを利用した化学実験を行い、研究されていることが面白かった、今後もこの講演者のお話を聞きたい、といったコメントが寄せられました。
カーボンニュートラルな社会の要となる触媒を探索する最先端の研究を知る貴重な機会となりました。
最後に、JAISTの大学案内のセッションでは、充実した環境で最先端の研究者とともに研究するという特徴や、新しい発見には分野融合的な考え方が必要との考えのもと、分野の転向も可能である点、学生の背景にあわせたコースワークを設定している点およびオープンキャンパス開催(11月15日)について紹介されました。JAISTへの推薦入学を希望するICUの学部生は学部事務グループにお問い合わせください。