メールマガジン Message from ICU, No.11 「バイリンガル教育の実践」
公開日:2022年11月30日人が人とのclose contactを避けなくてはならない。この異常な状況のなかでも、皆様とコンタクトを取り続けていきたい。そのような思いから、全国の中等教育に携わる先生方向けのメールマガジンを発行しています。なお、配信を希望される方は、以下よりお申込みください。
Message from ICU , No.11(2022年11月30日発行)
バイリンガル教育の実践
グローバル言語教育センターセンター長 藤井彰子
 ICUは献学以来、日英バイリンガル教育を貫いています。自分の社会の文化の常識を当然視することなく、未知の価値や思想に接して対話を重ね、他者との新たな関係の中に自己を見つめ直すことができる人材育成を目指しているからです。そのためには卓越したコミュニケーション能力が必須であり、日英両語の言語運用能力がまず必要となります。
ICUは献学以来、日英バイリンガル教育を貫いています。自分の社会の文化の常識を当然視することなく、未知の価値や思想に接して対話を重ね、他者との新たな関係の中に自己を見つめ直すことができる人材育成を目指しているからです。そのためには卓越したコミュニケーション能力が必須であり、日英両語の言語運用能力がまず必要となります。
 全ての学生が日本語と英語の両言語を使ってリベラルアーツで学ぶため、両方の言語でアカデミックな内容の文献を読み、講義を理解し、ディスカッションに参加し、課題を執筆する力が必要になります。英語力の強化が必要な学生は1、2年生の時に「リベラルアーツ英語プログラム(ELA: English for Liberal Arts Program)」を受講し、日本語を学ぶ必要のある学生は「日本語教育プログラム(JLP: Japanese Language Programs)」を受講します。
全ての学生が日本語と英語の両言語を使ってリベラルアーツで学ぶため、両方の言語でアカデミックな内容の文献を読み、講義を理解し、ディスカッションに参加し、課題を執筆する力が必要になります。英語力の強化が必要な学生は1、2年生の時に「リベラルアーツ英語プログラム(ELA: English for Liberal Arts Program)」を受講し、日本語を学ぶ必要のある学生は「日本語教育プログラム(JLP: Japanese Language Programs)」を受講します。
そして、各メジャーの授業を履修する際には、学生は授業内容や担当者を吟味し、英語で開講されている授業、日本語で開講されている授業の中から授業を選んで受講します。教員も必要や希望に応じて授業を日本語で開講することもあれば英語で開講することがあります。
「J」開講コース※1
 最近私が担当した一般教育科目「語学教育」は、約70名の学生が受講し、「J」科目として日本語で授業が行われました。「J」というのは緩やかな括りで、私が主に日本語で講義をし、授業中の活動では主に日本語使用するという意味です。英語の使用が禁止されているわけではなく、学生の学びをサポートするため、必要であれば、日本語に自信がない学生は英語で課題を執筆しても良いことにしています。今回は、参考文献はほとんど日本語でしたが、適当なものがある場合は英語の文献も入れます
最近私が担当した一般教育科目「語学教育」は、約70名の学生が受講し、「J」科目として日本語で授業が行われました。「J」というのは緩やかな括りで、私が主に日本語で講義をし、授業中の活動では主に日本語使用するという意味です。英語の使用が禁止されているわけではなく、学生の学びをサポートするため、必要であれば、日本語に自信がない学生は英語で課題を執筆しても良いことにしています。今回は、参考文献はほとんど日本語でしたが、適当なものがある場合は英語の文献も入れます
この科目は1、2年生が対象で、全体の半数以上の受講生は日本語以外の言語が使用されている教育環境(海外生活やインターナショナルスクールなど)を経験しており、多様な言語背景を持つ学生が集まっていました。それでも、日本語開講科目だったこともあり、受講者の大半は4月生でした。その内80%以上が英語よりは日本語のほうが得意だと回答していました。授業の中で、大学院生にゲストスピーカーとして修士論文の内容を発表してもらう機会がありましたが、英語で発表することを希望しました。ICUに入学したばかりの一部の学生にとっては初めて英語で生の講義を受ける、わくわくするような体験となったようです。
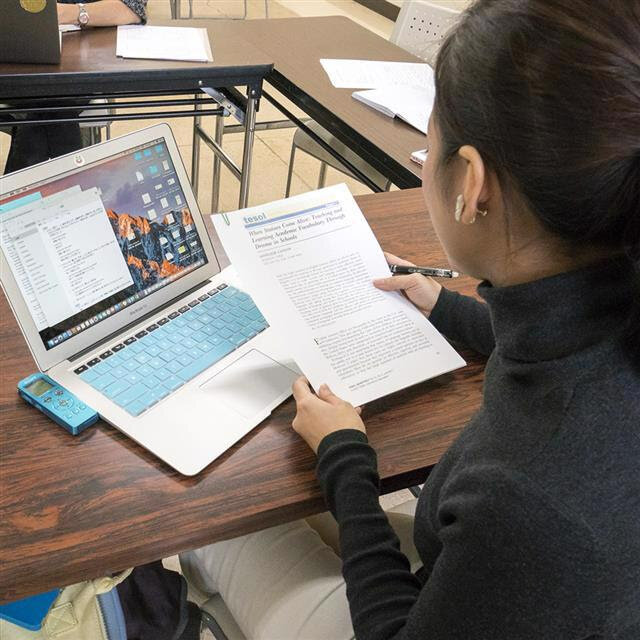 このような学生にとっては、日本語で受講する授業は、大学での学びを存分に満喫する時間となります。本授業で取り上げた問いの中には「英語の教員はネイティブ・スピーカーのほうが良いのか」あるいは「英語教育と社会格差の関係について」がありました。学生は第一言語である日本語で、自由に議論を交わし、文献を探し、考えをまとめることになります。それは、運用力の高い母語で深く考え、大学でのコミュニケーションに必要な語彙力、表現力、や論理的思考を身につけることができることを意味します。
このような学生にとっては、日本語で受講する授業は、大学での学びを存分に満喫する時間となります。本授業で取り上げた問いの中には「英語の教員はネイティブ・スピーカーのほうが良いのか」あるいは「英語教育と社会格差の関係について」がありました。学生は第一言語である日本語で、自由に議論を交わし、文献を探し、考えをまとめることになります。それは、運用力の高い母語で深く考え、大学でのコミュニケーションに必要な語彙力、表現力、や論理的思考を身につけることができることを意味します。
実は、この授業の受講者に10名ほど、日本語が母語ではなく、日本語教育プログラムを受講している学生もいました。この学生たちも日本語で授業に参加しますので、多様な仲間とディスカッションをします。お互いが日本語を駆使し、講義やグループディスカッション・プレゼンを通して活き活きとした学びが行われた学期でした。
「E」開講コース※1
私が「E」科目を担当する時は、この状況が逆になります。最近担当した「言語教育研究法」の授業は、言語教育分野で卒業研究を執筆予定の上級生(主に3年生)が対象のコースです。この授業では、講義、及びディスカッション、参考文献は主に英語でした。受講者11名の内、5名は日本で育ち、ICUへ入学する前は主に日本語で教育を受けてきました。1年生の頃から大きく成長し、堂々と英語開講の授業に参加している様子が見られました。他の学生は9月生で、ICUで初めて日本語を学んだという学生もいました。3名は長年英語の教育環境を経験していました。様々な言語背景のこの学生たちは一緒にグループ・プロジェクトに取り組み、調査研究の方法を学び、必要に応じて日本語と英語を使って助け合いながらデータを収集し、分析し、プロジェクトを仕上げ、発表しました。
[日本語を教育言語として学んできた学生]
ICUの「バイリンガリズム」とは単に英語ができるという意味ではありません。ICUでは日本語と英語両方の高い運用能力を理想としています。英語力のみを重視しているわけではないので、高校まで主に日本語で教育を受けてきた学生に関しては、第一言語である日本語のさらなる発達も期待されます。
 第一言語については、言語習得や教育の分野の研究者も重要性を主張しています。第一言語でのコミュニケーションスキルを育てることが第二言語でのコミュニケーションスキルの向上にもつながるとされています。また、第一言語が尊重されることが個人の自信にもつながります。日本語で教育を受けてきた学生にとって、ICUに入学し、先の例のように1年生の時から英語を学びつつ、日本語でも大学レベルの授業を受ける機会があることはバイリンガリズムにおいても重要なことだと考えています。
第一言語については、言語習得や教育の分野の研究者も重要性を主張しています。第一言語でのコミュニケーションスキルを育てることが第二言語でのコミュニケーションスキルの向上にもつながるとされています。また、第一言語が尊重されることが個人の自信にもつながります。日本語で教育を受けてきた学生にとって、ICUに入学し、先の例のように1年生の時から英語を学びつつ、日本語でも大学レベルの授業を受ける機会があることはバイリンガリズムにおいても重要なことだと考えています。
[英語を教育言語として学んできた学生]
長年英語を話す家庭で育ち、また英語の教育環境にあっても、大学レベルの課題に取り組むには特別な教育が必要なのです。また一見日本語が流暢に見える学生でも、海外生活中に吸収し損ねた日本語を補填する必要があることもわかってきました。メディアで目にする二言語で育った羨むべき存在としての「バイリンガル」を体現するような学生も、実はどちらの言語も第一言語だと感じられない不安定な状況に置かれていることがあります。 幸いICUでは日本語教育プログラムの科目を履修することで、ニーズにあわせて漢字を学び、語彙を増やし、大学レベルの日本語文献を読み解くスキルを身につけることができます。このようにアカデミックなレベルでバイリンガルになるというのは努力を要し、自然に備わる素質ではないことがわかります。
 ICUは国際社会から学生を本科生として受け入れており、入学前の日本語レベルがゼロであっても日本語教育プログラムを履修して大学レベルの科目を学ぶ日本語運用能力を身につけることが出来ます。もちろん、これは簡単なことではなく、教員と学生双方のコミットメントが必要です。多くの学生がICU入学後の日本語教育プログラムでの厳しい指導を経て、バイリンガルの素養を育んでいきます。
ICUは国際社会から学生を本科生として受け入れており、入学前の日本語レベルがゼロであっても日本語教育プログラムを履修して大学レベルの科目を学ぶ日本語運用能力を身につけることが出来ます。もちろん、これは簡単なことではなく、教員と学生双方のコミットメントが必要です。多くの学生がICU入学後の日本語教育プログラムでの厳しい指導を経て、バイリンガルの素養を育んでいきます。
語学プログラムを経て、それぞれの学生が第二言語(あるいは第三、第四言語)である日本語や英語での授業を多く履修することになると、本当の意味でのバイリンガルなコミュニティーの様子が見られます。学生に英語と日本語の開講科目の履修を義務付けていることで、両方の言語でアカデミック・スキルを身につけてもらい、共に学ぶことが可能になるわけです。先に紹介した授業では学生たちが助け合う姿も多く見られます。苦労しながらも全員が日英両語でアカデミックな内容について理解し、議論し、文章を執筆出し、「J」と「E」科目を共に履修できることが重要です。学生たちが共に生活し、共に学び、共に対話することがICUのバイリンガルだと私は考えています。
※1:「J」開講コース、「E」開講コース
「J」は日本語でその授業が行われることを表します。「E」は英語でその授業が行われることを表します。ICUでは、「J」「E」はコースによって定められるのではなく、担当教員が決定します。コースによっては、ある学期は「J」開講、別の学期には「E」開講というコースもあります。特に「J」開講コースにおいては、受講生の日本語運用能力によって、担当教員の判断で、英語による質問やレポートや試験を英語で提出することを認めるといった配慮を行っています。
グローバル言語教育センター センター長 藤井彰子
2006年ジョージタウン大学で言語学博士号取得(Ph.D.)。専門は言語教育。第二言語の習得・学習プロセス、英語教育における教授法の理論と実践など。2016年 ICU着任。2018年から「IB 教員養成プログラム委員会」委員長を務め、2021年9月からグローバル言語教育研究センター長。