学部・大学院案内(パンフレット)
ICU入学案内「2024」Web特別コンテンツ
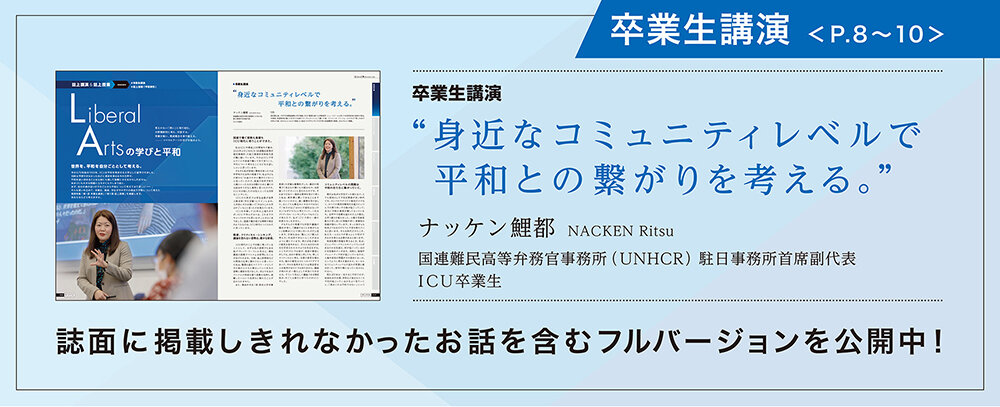
▼
身近なコミュニティレベルで 平和との繋がりを考える。
国連で働く情熱も基礎もICU時代に培うことができた。
私はI CU 卒業後21年間海外で働き、2021年よりUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の駐日事務所首席副代表の職に就いています。今日はICUで学んだことや国連で働いてきて思うこと、平和について考えることなどをお話ししたいと思っています。
そもそも私が国連に興味を持ったのは中学校の社会科の授業です。私は子どもの頃から「お金のために働きたくない」と思っていたので、国連で世界平和や人権といった大きな目標のために働くのは面白そうだなと漠然と思ったのです。ICUを目指したのは私にとっては自然なことでした。
ICUの入学式では学生全員が世界人権宣言(学生宣誓)にサインします。入学前にそれを聞いて「やはりこの大学はすごいな」と思ったのを覚えています。
ICUを卒業して20 年以上経ちますが、ICUで学んだ日々は、これまでのキャリアの中でも思い出すことがよくありました。国連で働き続ける情熱や信念のようなものは、ICU時代につくられたと思っています。
熱意、クリティカル・シンキング、議論を恐れない姿勢は、確かな財産。

ICU 時代のことで印象に残っていることとして、まずは私の恩師でもある故デヴィッド・ワーフェル先生と、現地調査の授業でベトナムを訪問したことがあげられます。当時、途上国開発などの開発の仕事に関わりたいと思っていた私は、職業を超えライフワークとしてその国の人たちと関わっていく先生の姿勢に感銘を受けました。何より先生のベトナムの発展を願う真摯な気持ち、貢献したいという気持ちに触れたことが忘れられません。
また、姜尚中先生( 現 東京大学名誉教授)の言葉も衝撃的でした。最初の授業で「見るもの聞くもの読むもの、全部疑ってください」と言われたのです。それまで日本の一般的な教育を受けて育っ
た私は、教科書に書いてあることまで疑っていいのかと、強い衝撃を受けました。なにごとも鵜呑みにするのではなくて「本当かな」「ほかに可能性はないのか」「なぜだろう」と考えていく。これはクリティカル・シンキングというものごとの考え方で、私がICUで得た一番の財産かもしれません。
そもそもどの授業でも対話や議論の機会が多く、「議論することを怖がらない」姿勢はI CU で身に付いたのだと思います。日本社会は「個人」と「個人の考え方」を区別できないところがあるように感じています。例えば私が誰かの意見を批判すると、その人は自分の存在を否定されたかのような反応をする。ところがICUでは皆が、他者の意見に対しても、自分の意見に対しても、等しくクリティカルに考え、全員で意見を戦わせる。誰かの意見はひとつのアイデアであって、それを批判することは発言者本人を批判するわけではありません。議論が終われば一個人として仲良く付き合える。そういう安心して議論できる関係性が、すごく大事だと学べたのがICUでした。
環境問題を学んでいくと、そこに人権や差別の問題が見えてきた。
ICU時代、課外活動として、他大学の学生と一緒に活動するインターカレッジ
のサークルで環境問題を勉強していました。当時リオの環境サミットがあり、若者の間でも環境問題への関心がすごく高まった時代でした。実際に世界を見てみようと、ドイツの先進的な都市やポーラ
ンドの環境整備の現場などを見に行きましたし、日本の公害問題についてもかなり勉強しました。
これらの経験を通して、課題解決へのアプローチについて深く考えさせられました。足尾銅山や水俣病の勉強をしたときに、企業や社会全体のルールの問題だけでなく、ローカルなレベルで生じている人権や差別の問題に目を向けることが重要だと気付いたのです。被害者の声をいかに真摯にくみ取り救済できるか、なぜそれができなかったのか。こうした問題を考えることが問題の本質や、解決へのアプローチにも密接に関わっているのです。目に見える問題の裏に、それと密接に絡み合う別の問題があるということに気付かされました。
コミュニティレベルの問題は平和の在り方に繋がっていく。
現代は私が大学生だった頃と比べ、とても混沌として不安定要素が多い時代です。ロシアのウクライナ侵攻だけでなく、かつての東西冷戦時代を超えたレベルでの勢力争いや分断が起こっていて、本当に平和の実現が難しくなっています。世界中で故郷を追われた人の数は、去年1億人を超えました。人権や気候変動など差し迫った問題が多く、普遍的な価値が揺らいでいます。きっと皆さんも将来どうなるのだろうと不安を覚えていると思います。そんな時代だからこそ、私たち一人ひとりが個人として何ができるかを考える必要があると思います。
地球規模の問題を考えるとき、私は、どこにパワーバランスやインバランスがあるのかを見据え、何が起こっているのかを見極めていきます。同時に、地域や国連で働くことについてなど、冊子に掲載しきれなかったお話もご紹介します。コミュニティで何が起こっているのか、人権や差別の問題がその根本にないか、というように考えを進めます。学生時代、足尾銅山や水俣病など公害問題に向き合った経験がこうした思考の原点です。
ローカルなコミュニティレベルの歪みが密接に絡み合って、紛争の種になっているかもしれない。
例えば日本は一見すると平和ですが、地域社会や企業、学校など身近なところで何が起こっているかをよく見ていくと、「実はこれは平和ではない」ということがいろいろあると思います。どんな問題があって、その問題がどうして起こるのか、他のどんな問題と繋がっているのか、そして自分には何ができるだろうと探っていく。コミュニティレベルで問題を把握し解決策を考えていくと、自分ができることがあるかもしれない。このアプローチがすごく重要だと思います。それがひいては地域の安定と平和に繋がっていきます。
ジェンダーと平和。Gender and Peace

私自身も日々、本当に全てのことが繋がっていると感じています。例えば「女性と平和」あるいは「ジェンダーと平和」という繋がりについて、考えたことが
ある人はいますか? 実は国連の安全保障理事会では、女性が主体となって平和構築、平和維持、紛争解決などに関わっていかなければ平和は維持できないとされています。これは「平和と女性の
役割」という決議( Women, Peace and Security「女性・平和・安全保障に
関する国連安保理決議第1325 号」)として世界で共有されています。
私もUNFPA(国連人口基金)で活動した際には、この決議をスリランカの
社会にインプリメント(実行・実装)することを目的に、主として「性と生殖に関わるプロジェクト」に取り組みました。具体的には、性教育や、ジェンダーに基づく暴力に関する啓発活動や被害者のサポートなどを行いました。
それが平和とどう関係するのか、疑問に思われる方もいるでしょう。スリランカではシンハラ族とタミル族の間で26年間も内戦がありました。現在では少数派であるムスリムへの攻撃や過激組織によるテロ事件などもあり、さらに社会が複雑化しています。こうしたコミュニティ間の衝突は、実は女性のリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性や身体のことを自分で決め、守ることができる権利)にも密接に関わっています。私が赴任した頃に始まった衝突も、発端は出産に関わるデマでした。「少数派のムスリムが多数派シンハラ族の食事に避妊薬を入れている」「人口を逆転させようとしている」というデマがSNSなどで一気に広がり、ついには暴動に発展しました。
平和に反するような暴力が、性と生殖に関わる問題を発端とする例は他国にもあります。そして、アメリカの中絶反対の運動に見られるように、非常にポリティカルに扱われやすい問題です。女性の自己決定権が守られない社会は、平和に繋げていくことが困難な社会だと私は考えています。そこでは一人ひとりが自分の可能性を使って自分の人生をつかみ取ることができない。だれもが自分の選択をつかみ取れる環境であること、それが平和にはとても大事なことです。
国連で働くということ
さて、今回の講演会前に取ったアンケートでは学生のみなさんから国連で働くことへの質問が多くありましたので、ここで国連を職場とすることについて、お話ししたいと思います。
ICU には、国連勤務の卒業生が多く、皆さんの中にも国連志望の方が多いと聞いています。そんな皆さんにお伝えしたいのは「国連で何がやりたいのか」をしっかり考えてほしいということです。その仕事は国連でなくてもできるかもしれない。例えば気候変動にとても興味があるならば、国連でなくてもNGOや他の機関でも取り組める。まずは何をやりたいか、何に情熱を感じて、何を原動力とするのか。それが土台になければ本当に重要な決断はできません。
国連は大きな官僚組織ですから堅苦しさもありますが、私が今まで4 つの国連機関で働いてきた経験からは、「官僚組織ではあるけれど、自分のイニシアティブで動くことが許される」、「こうやりたいと思ったら動ける」、そんな環境があると思います。逆に言えば、受動的では務まりません。何か面白いことが降ってくるのを待っている姿勢では、自分が成長できないばかりか生き残れないでしょう。世界中から人が集まる競争社会なのです。どんどん自分で自分の仕事をデザインしていく、積極的な姿勢がすごく大事です。
私の場合は、ステップアップとはいえなくても、自分の優先順位に照らして納得できるものがあると感じたときに新しい仕事に挑戦しています。具体的には、私は新しいことを学ぶのが好きなので、別の機関でどれだけのことを新しく勉強できるか、自分はどういった貢献をすることができて、何を得ることができるかを考えてきました。また、世界中を移動していくことになるのもしっかり考えておく必要があります。家族を連れて行けない赴任先もあるので、単身赴任でも自分や家族がハッピーでいられるかは非常に重要な判断基準です。繰り返しになりますが、自分は何をしたいのか、自分の原動力や本当の希望を知るために、自分の気持ちをどんどん深く掘り下げていくことが不可欠なのです。
できることを少しずつ。その一歩を対話から始める。
国連が行うようなプロジェクトでなくても、私たち一人ひとりが関われる平和への一歩はきっと身近にあるはずです。意外と身近に、難民や移民の背景を持っ
ている方もいるかもしれません。彼らの声を聞いてみることから始めてみるの
も良いと思います。まずは身の回りを見渡してみてください。例えば、友人同士
の仲たがいがあったとすれば、その背景に何があるのか。人と人との衝突や摩擦
はなぜ起こるのか、どういう解決があり得るのか、ぜひ友人や家族とも話してみ
てほしいと思います。
ICUではさまざまな分野を専攻する学生が、それぞれの視点や問題意識を持ち、それぞれのアプローチからさまざまな問題について語り合う環境があります。これが重要です。平和に繋がる動きは
まさにそこから始まっていくと思いますし、そこからしか始まらないと思います。
恐れずに、クリティカルに考え、対話や討論を重ねてください。分野や学年を超え、
先生方や新入生たちとも対話を続けてほしい。自分は何ができるのか考え、少
しでも行動に起こしてみる。そういったことが平和への一歩になるはずです。
最後に私の大好きなマーガレット・ミード(文化人類学者)の言葉を紹介して、私の講演を終わりにしたいと思います。国連で働いていても実感する言葉です。今日はありがとうございました。
Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world.
In fact, it's the only thing that ever has.
思慮深く献身的な、少数の市民が世の中を変えられることを疑ってはなりません。実際に世の中を変えてきたのは、そういう人びとにほかなりません。

ナッケン 鯉都
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)
駐日事務所首席副代表
ICU卒業生
<プロフィール> 東京都出身。1997年国際基督教大学卒業後、NGO勤務を経て大学院留学( ニュースクール大学)で非営利団体の経営を専攻。卒業後、国連開発計画(UNDP)の本部でコンサルタントとして働いた後、スリランカ・ベトナム・エチオピア等これまで世界6カ国、20年以上にわたり国連人口基金(UNFPA)やUNDP 等の国連機関で勤務。2021年より現職。

ICU入学案内「2024」(学部)
ICUの特色や学びを中心に、ICUの特徴であるLiberal Artsを体験し、知ることができるパンフレットです。
※ 送付を希望される方は、送付希望の方よりお申込ください。
