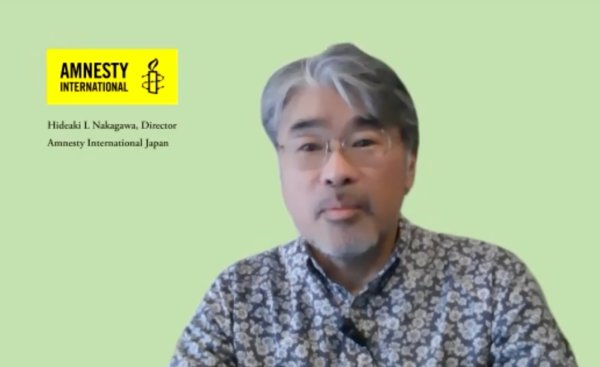NEWS
地球市民社会論シリーズ「社会的インパクトをめぐる世界の潮流」
公開日:2021年3月1日
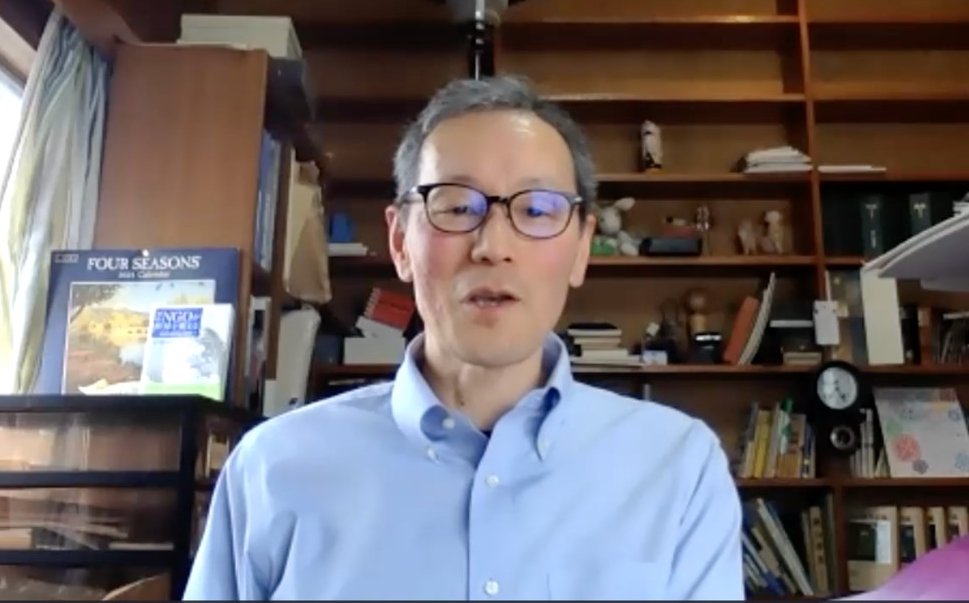
2月26日(金)、教養学部専攻科目「地球市民社会論」(担当:毛利勝彦教授・国際関係学メジャー)の第5回学内公開講演を開催しました。CSOネットワーク常務理事の今田克司さんに「社会的インパクトをめぐる世界の潮流〜新しい資本主義は社会を良い方向に変えるか」というテーマでお話いただき、80名ほどの学生が参加しました。今田さんは、社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ代表理事やSDGs市民社会ネットワーク業務執行理事も務められています。
講演は「新しい資本主義は何か」という問いから始まりました。そして冷戦終結、リーマンショック、国連持続可能な開発目標(SDGs)採択、新型コロナ感染症などによって、3つのセクター(政府セクター、民間営利セクター、民間非営利セクター)の役割がいかに変化し、理解されてきたかが解説されました。大企業を中心に、社会貢献、企業の社会的責任(CSR)、共通価値の創造(CSV)を経て、企業価値概念が再考されるようになっていることが指摘されました。金融・投資においては、社会的責任投資(SRI)、ESG投資、インパクト投資などのキーワードからその変遷を追い、社会セクターにおいても社会的起業・企業が台頭していることが読み解かれました。
さらに先進事例の紹介とともに、株主資本主義からステークホルダー資本主義へとリセットされつつあることが紹介されました。SDGs採択後の世界では、次々に噴出する課題解決に向けて、公的機関、民間営利企業、民間非営利団体を問わず、共通の目標やターゲットでそれぞれの活動の社会的インパクトを意識し、検証するマネジメントが重要になっていると結論づけられました。
講演会に参加した学生からの感想
・株主資本主義とステークホルダー資本主義の対比は、20世紀と21世紀との異なる資本主義の考えを表していて分かりやすかった。積極的に提唱され始めた脱炭素社会は、背後に政治的な動機や利権があるとはいえ、ステークホルダー資本主義が市民権を得た実例であると思う。
・社会セクターへの注目を通して、人道的・倫理的価値がその時点での社会的評価のトレンドを左右する変遷が面白い。個人的には、株主や会社だけでなく広範囲の公的な「利益」を追求し、持続可能な社会を意識しているかどうかを、就職先を決める際の指標にしたい。
・ポジティブインパクトの可視化や、「非営利」団体や「非政府」組織といったネガティブワードではない「市民社会」団体という言葉で表そうとしていることを考えると、市民社会の方向性は、マイナスを見るのではなくプラスの側面に光を当てる傾向にあると思いました。
・日本では最近急激にSDGsへの意識が高まり、「SDGs」という単語をニュースや新聞で見ることが増えている。大企業や政府機関など様々な分野の人々ができる範囲で共通課題に取り組むことが欠かせず、市民が社会問題について注視していることを知れば自ずとステークホルダーの活動は変容していくと思う。今後の課題はこうした活動をどのように長期的に評価するか、環境問題など喫緊の課題をどう迅速に成果を上げるかだと感じた。