株式会社ファーメンステーション代表取締役
1995年 国際関係学科(当時)卒業
「自分がやりたいこと」と「社会に役立つこと」を追求し、
ようやく見つけた「発酵」の世界

「発酵」の力でサステナブルな社会を作る
私は現在、発酵技術によって「未利用資源」を新たな商品やサービスとして再生させる「ファーメンステーション」という会社を経営しています。たとえば休耕田から育てた米、規格外の農作物、ジュースの搾り粕などを発酵させてエタノールなどの機能性素材を製造し、化粧品などの原材料などに使用。残った発酵粕は飼料として活用し、さらにその鶏糞は田畑の肥料として使用します。こうしたサステナブルな循環が当たり前になる社会を作るのが、私たちの目標です。
起業した2009年当時は、サステナビリティという概念が今ほど世間に浸透していませんでした。作ったエタノールは価格の高さがネックとなり全く売れず、事業内容を説明しても「市場性がない」と言われるばかり。長い間、資金繰りに苦労しましたが、それでも「いつか時代が追い付く」と信じて事業を続けてきました。SDGsが策定され、人々もエシカルな消費行動を意識するようになった今、まさに時代の流れは私たちに向いてきていると感じます。
事業を通じてアプローチできる社会課題は、フードロスだけではありません。石油の代替燃料を製造できる発酵技術は、"脱石油"のものづくりにも役立ち、地球温暖化対策にも貢献できます。私たちの技術で、地球規模のさまざまな課題を解決できる可能性がある。そんな壮大なチャレンジができることに、やりがいを感じています。
こうした"事業性"と"社会性"を両立させたビジネスを実現したいというのも、起業時から私の根底にある思いです。まだこの両立に懐疑的な人も多いですが、それができると証明するためにも、私たちが成功することは大事だと思っています。これからも循環型社会の構築を目指し、国内外に事業を拡大していきます。
バラバラだったピースが一気につながる感覚
美しいキャンパスを持つICUには中学生の頃から興味を持っていました。ICUに入学すると多くの勉強量が求められると聞いていましたが、その点も私にとって魅力的でした。自分が大学で遊び呆けてしまわないよう、そうした環境に身を置くのが良いと思ったのです。また、受験生の思考力が試される、ICUならではの入試問題を見て、絶対に面白い学びが実現できる大学だと感じたことも、志望理由のひとつでした。
ICUに入学して驚いたのは、学生の多様性です。私の出身は中高一貫の女子校で、高校まではある意味でクローズドな環境で過ごしていました。一方、ICUには国内外さまざまな地域から、いろいろな興味関心を持つ人たちが集っている。お互いを尊重し、対等に話し合っている。そんな誰もがオープンでいられる環境に感銘を受けました。私は「変わっている人」に魅力を感じ、そういう人が世界を変えると思っているのですが、この価値観は間違いなくICUの環境で育まれたものだと思っています。
ICUには「世の中の役に立ちたい」と考えている学生が多く、私もそうした思いを抱きながら、さまざまな科目を履修しました。中でも国際関係学科(当時)の横田洋三先生が担当されていた海外フィールドワークの授業は印象に残っています。各々が好きなテーマを設定し、海外で3週間ほどのフィールドワークを経て、英語で論文にまとめるという経験は、とても刺激的でした。しかし、在学中に自分が本当にやりたいことは見つけられないまま、ICUの先輩から勧められた銀行への就職を決めました。
銀行では、後につながる多くの経験を積むことができました。出向先の国際交流基金でNPO支援事業を担当し、社会課題に取り組む企業の存在を知ったことは、今の事業活動の原点となっています。また、エネルギー開発やインフラ事業への融資を行う部署で「環境評価」という視点を得たことも大きかったですね。インフラ整備などは環境負荷が大きいため、融資の際に採算性だけでなく環境へのリスクも考慮して評価を行うのです。これが面白く、環境問題にまつわる分野に自分のやりたいことがあるのではないかという予感を抱きました。
銀行での仕事は充実していたのですが、やはり自分にしかできないビジネスがしたいと思い、6年で退職。いくつかの企業を転々とするなかでそれぞれ刺激は受けたものの、心からやりがいを感じる仕事にはなかなか巡り合えませんでした。ICUの友人が目標に向かって着実にキャリアを積んでいる中で、私は進むべき道さえ見つかっていない。そのことに、強い焦りを感じていたことを覚えています。そんな時、海外出張先でルームサービスの食事を頼んだ際に、食べきれない量のパスタが出てきたことがありました。生ゴミとなってしまうであろうパスタを目の前にして、ふと強い疑問を抱いたのです。「大量のゴミを無駄に出し続ける社会が、このまま続いていいのだろうか」と。
そうした折に、たまたま流していたテレビ番組で、東京農業大学の「生ゴミを発酵させてエネルギーに変える」研究のことを知ったのです。発酵の力を使えば、世の中にあふれるゴミを有益なものに変えられる。これまでバラバラだったピースが一気につながっていく感覚があり、「これだ!」と直感しました。
勤めていた会社を辞め、迷わず東京農業大学に入学。職場の人には驚かれましたが、ICUの友人たちは「面白そう、いいね!」と応援してくれました。4年間、発酵技術を一心不乱に学び、2009年に起業。大学の研究室のつながりで、岩手県奥州市との実証実験「コメからエタノールと餌をつくる地域循環プロジェクト」を受託したことを皮切りに、ファーメンステーションは企業としての一歩を踏み出しました。
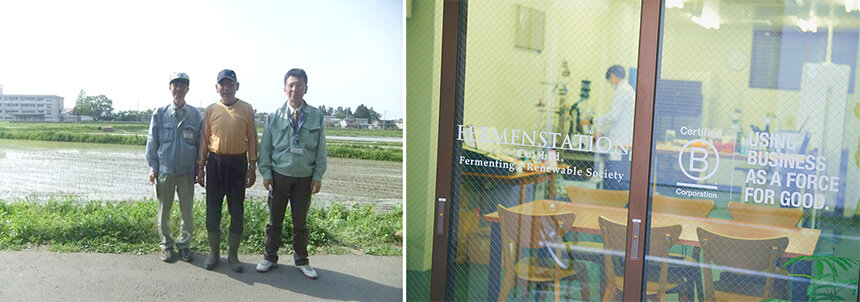
写真左:生産農家と市役所のみなさん 写真右:会社の様子
生き方そのものが、ICUをベースに形作られている
会社や事業のことを友人に話すと「ICUっぽいね」と言われることがよくあります。多様なメンバーの個性を認め合う社風や、多彩な分野にまたがる事業内容が、ICUの学びの環境に似ているのかもしれません。
また、ファーメンステーションのステークホルダーは、生産農家、飲食会社、アパレル会社、コンサルタントなど非常に多岐にわたります。それぞれの業界で文化やスタイルが異なるため大変なこともありますが、好奇心をもってオープンに関わるとすごく楽しい。先入観を持たずに、いろいろな知識やものの見方を吸収していくと、会社にも自分にもプラスの影響を与えてくれるのです。こうした姿勢は間違いなくICUで得られたものであり、自分でも驚くほど、私の生き方そのものがICUをベースに形作られているのだと実感します。
私は「発酵」という分野に出会うまで、自分のやりたいことがなかなか見つからず、辛いと感じる時期が長くありました。だからこそ、こうした経験から後輩の皆さんに向けて言えるのは「やりたいことがすぐ見つからなくても、焦らなくていい」ということです。
今の大学生は、在学中にインターンシップの機会が多くあるなど、早い段階から将来を考えることが求められている気がします。しかし、その時々で目標は変わるものですし、いくら考えても答えが見つからないこともあります。だから、自分自身や周囲に常にアンテナを立てて、考えることを諦めないでいてほしいのです。「どんなことが好きなのか」「何をすることが自分らしいのか」と常に考えていると、チャンスに出合うタイミングが必ず来ます。自分が夢中になれるものが見つかると、人生はより豊かになると私は思っています。

ファーメンステーションのメンバーと
Profile
酒井 里奈
株式会社ファーメンステーション代表取締役
1995年 3月国際関係学科(当時)卒業
ICU卒業後、株式会社富士銀行、ドイツ証券株式会社などに勤務。その後、発酵技術に興味を持ち、東京農業大学応用生物科学部醸造科学科に入学。2009年3月卒業。同年、株式会社ファーメンステーション設立。




