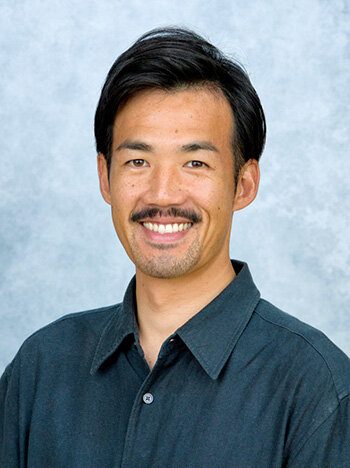オーストラリア、エマニュエル・カレッジ教員
2012年3月 教養学部卒業(メジャー:メディア・コミュニケーション・文化、マイナー:言語教育)
異なる価値観、文化を尊重できる人材を育成したい
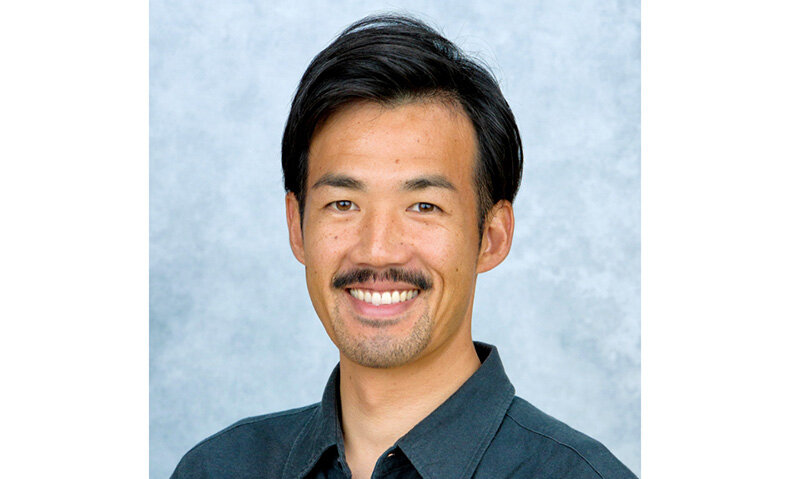
日本語教員として 生徒の成長を間近で支えられる喜び
現在、オーストラリアのエマニュエル・カレッジで日本語教員を務めています。同校は、セカンダリー・スクールという日本の中学校・高等学校にあたる教育機関です。私はICU在学中に日本語教員養成プログラムを受講し、この道を志しました。ICUを卒業して、オーストラリアで日本語補助教員を1年間経験した後、現地の大学院のMaster of Teaching(教育学修士)でオーストラリアの教員免許を取得し、現在に至ります。
私が勤めている学校では、中学1・2年の時に外国語科目(日本語かフランス語)が必修で、半年間は全員が日本語の授業を受けます。中学3年以降は、外国語の学習を続けるか、続けないかを選択できます。高校3年まで日本語の授業を履修する生徒は、日本の姉妹校への交換留学や日本での学習旅行に参加する機会も。このように日本語教育が盛んな環境ですが、日本語への関心が薄い生徒もいるため、まずは楽しんでもらおうと、日々工夫を重ねています。日本語の文字には平仮名、カタカナ、漢字の3種類があり、難解な言語だと思われがちです。しかし、文法は意外とシンプルな側面もあり、そういったことも含めて日本語の面白さや魅力を生徒に伝えています。教員同士の勉強会にも積極的に参加し、教授法について意見交換するなど、教師として常に勉強する姿勢を心掛けています。
やりがいを感じるのは、やはり生徒たちの成長を実感した時です。入学したばかりの頃、平仮名や漢数字などを一生懸命学んでいた生徒が、卒業時には日本語でディスカッションし、長文も書けるようになっている。そうした姿を見ると、この仕事に就いて良かったとつくづく思います。「先生のおかげで将来の目標ができた」「日本で翻訳者として働きたい」「オーストラリアで日本語を教えたい」といった生徒の声を聞くと、さらにうれしさが込み上げます。セカンダリー・スクールの教員は日本の一般的な中高の教員と同じように、担当クラスを受け持ち、ホームルームや面談、生活指導などを行います。多感な時期にある彼らの成長を間近で支え、人生のターニングポイントにも立ち合うことができるのは、この仕事の醍醐味といえるでしょう。

左:学校のウェブサイトから、右:学習旅行で訪れた広島で生徒たちと
多分野の学び、人々との出会いに恵まれ 将来の目標が定まったICU時代
ICUを志望したのは、キリスト教の精神に基づいて国際的社会人を育成することを使命に掲げ、多彩な領域に触れられるリベラルアーツ教育を行っている点に惹かれたからです。海外志向を持ち、幅広く学ぶ中で将来の方向性を模索したいと考えていた私にとって、魅力的な進学先でした。
入学後、多様な分野の科目を履修する中で、日本語教育に関する授業に惹かれました。それまで無意識に使っていた日本語ですが、文法などを論理的に理解し、他者に分かりやすく説明する点に強く興味を覚えたのです。そして、指定の科目を一定数履修することで修了証が得られる「日本語教員養成プログラム」の存在を知り、より力を入れて学びました。
現在の道に進む決意が固まったのは、3年次にオーストラリアでの教育実習に参加した時です。約1カ月間、現地のセカンダリー・スクールで日本語を教える中で、生徒の成長を肌で感じられる仕事に大きな魅力を感じるようになりました。ワークライフバランスを重視した働き方にも惹かれ、オーストラリアで日本語教員になりたいと心が決まったのです。
ICU在学中は日本語教育以外にも、さまざまな学問領域に触れ、多角的に物事をとらえる重要性を実感しました。特に印象的だったのが、メディア・コミュニケーションに関する授業です。常にマイノリティや弱者の視点に立って考える姿勢は、教員となった現在も自分のベースとなっています。
ICUでは日頃から外国人留学生と接する機会が多く、異文化理解や多文化共生にも興味を抱くようになりました。ICUに通う日本人学生も、帰国生や、日本にいながら海外式の教育を受けてきた人などさまざまで、「日本人ならこうあるべき」という固定観念が覆されました。国際寮で過ごし、多様な国籍・バックグラウンドを持つ学生と共同生活を送ったことも、かけがえのない経験に。寮で出会った仲間は家族のような存在で、現在も親しく交流しています。寮生活を通じて、実践的な英語はもちろん、チームワークやリーダーシップも学ぶことができました。入学前は英語が得意ではなかったのですが、いま英語を使って海外で仕事ができているのは、ICUの環境のおかげだと感謝しています。

左:オーストラリアでの教育実習、中:寮の仲間と、右:ICU祭にて(写真右が太田さん)
視点を変え、困難を前向きにとらえる姿勢を大切に
今後もオーストラリアの中高生に日本語を教えながら、教員としてさらなる成長を図りたいと考えています。もっと多くの生徒に日本語を好きになってもらえるよう、身体を使ったアクティビティやゲーム、ITを授業に取り入れるなど、日々試行錯誤しています。ここでも生きているのが、ICUの先生方から受けた授業の経験です。一方的に講義を聞くのではなく、ディスカッションベースで能動的に学ぶ。こうしたICUの授業スタイルを、もっと自分の授業にも取り入れていきたいと思っています。
オーストラリアで日本語教育に携わって10年以上が経ちました。根底にあるのは、「日本語能力だけでなく、異文化理解や多文化共生を大切にするマインドを育てたい」という思いです。たとえ語学が得意でなくても、異なる価値観や文化を尊重できる人が一人でも増えると、より平和な世界になっていくのではないでしょうか。また、私自身も日本や日本人のステレオタイプを生徒に押し付けず、「日本にはこういう人もいる。こんな文化もある」と多様な側面を伝えていきたいと思っています。
ICUで学ぶ皆さんの中には、いずれ海外で働く方もいると思います。海外生活は不便な点も多いですが、ただ「大変」で終わらせるのでなく「困難をどう乗り越えるか」とうマインドが大切です。カルチャーショックを受けたままにせず、「これから知っていこう」と思考を切り替えられると、なお良いと思います。そのためにも、ICUでさまざまな考え方や価値観に触れ、多くの経験を積み、視野を広げていただきたいと願っています。
Profile
太田 宗
オーストラリア、エマニュエル・カレッジ教員
2012年3月 教養学部卒業(メジャー:メディア・コミュニケーション・文化、マイナー:言語教育)
ICU入学後、日本語教員養成プログラムを履修。卒業後、オーストラリア政府公認の「Language Assistants Program(LAP)」で1年間、日本語補助教員を務めた後、フェデレーション大学でMaster of Teaching(教育学修士)を取得。現在、エマニュエル・カレッジの教員として「日本語」「メディア」の授業を担当。