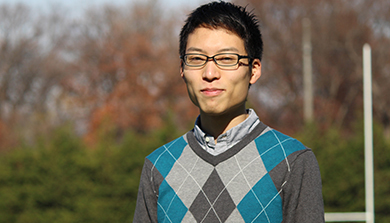メジャー:平和研究

【シリーズ:留学✕リベラルアーツ 第2回】
2国間の比較を超え、世界を舞台にした「核をめぐる対話」へ
平和研究メジャーの佐藤優実さんは、ドイツのベルリン自由大学に1年間の交換留学中です。
3回にわたるインタビューを通じて、留学生活の中での変化を探るシリーズ企画。
今回は第2回として、留学開始から半年が経った佐藤さんにお話を伺いました。
ベルリン自由大学での本格的な学び
10月末からベルリン自由大学での授業が始まりました。現在はドイツ語の授業に加え、国際機関について英語で学ぶ科目や、ヨーロッパの比較政治学などを履修しています。国際関係学について文献を熟読する他、学生同士で議論をしたりプレゼンテーションを行ったりとアウトプットの機会も豊富です。また、「チェルノブイリと福島」という科目では文学的な観点から両者を考察し、自身の研究テーマである核問題について視点を変えて捉えなおす機会となりました。
授業ではリーディングとライティングが課され、予習・復習に追われる日々。学期末には6000wordsのレポートを仕上げる予定です。大学入学前には想像もつかなかった量ですが、ICUのELAプログラムで文章構成や文献の引用方法を学び、基礎を固めたからこそ抵抗なく取り組むことができています。さらに、履修しているすべての授業でプレゼンテーションの機会があります。人前で話すのは緊張しますが、ドイツ語での発表にも徐々に慣れてきました。他の学生の意見を聞くことも大きな刺激になっています。

ドイツでの半年を経て、定まった研究テーマ
留学以前は日本とドイツの比較研究を計画していましたが、ドイツで学ぶにつれて徐々に核問題へと興味関心の軸が移っていきました。2国間の研究ではなく、世界から核をなくすための国際的な「対話」に向けて何をしたらよいのか、追究したいと考えるようになったのです。
こう思ったきっかけのひとつに、ドイツでのショッキングな発見がありました。それは、世界で広島に対する「誤解」が残っているという事実です。以前、クラスメイトから「まだ広島には放射能が残っているんでしょ?」と聞かれたことがありました。衝撃を受けながらも、誤解を解くため「残っていないよ」と説明しましたが「放射能は長く残る」という認識は、なかなか覆りませんでした。核や放射能に対する知識、説明力不足をもどかしく感じたことを覚えています。国際関係学や政治学を学ぼうとドイツに来ましたが、この経験を機に、核の種類や破壊力など技術的な面からも学びたいと考えるようになりました。
さらに、近年のウクライナ戦争の動向も、核研究への後押しとなりました。核兵器が使われうる状況の中で、広島のような悲劇を二度と起こしてはいけないという決意が一層強くなったのです。しかし、一方的に核廃絶を主張するばかりでは物事は進展しません。核のない世界を実現するためには核保有国との「対話」が不可欠です。
そこで、ドイツから日本に帰国してICUを卒業した後には、アメリカの大学院へ進学したいと考えるようになりました。核をもって戦争を防ぐ「核抑止」の考え方を持つアメリカで、今までとは異なる視点から核を学び、平和のための対話に繋げるためです。このように思い至った背景には、対話を重視するICUのリベラルアーツ教育で学んだ経験があると感じています。
ICUリベラルアーツが、留学生活をさらに豊かにしてくれた
ベルリン自由大学は約3万人の学生が在籍する大規模な大学ですが、学生数に比例して教員数も多く、日頃のコミュニケーション量はICUに近いと感じます。一方、12の学部ごとに使う建物が分かれており、それぞれが専門に特化している点は、ICUとの大きな違いと言えるでしょう。
その中で私は、リベラルアーツで学んだICUでの2年間の大切さを実感しています。ICUでは日常的に友人とお互いの専門分野について話す機会があります。そんな時には、広範な基礎知識が相手の話を理解し、掘り下げることに役立っています。また、ドイツで信仰する人が多いキリスト教は、日常会話の中で度々話題にあがるトピック。ICUで「キリスト教概論」(一般教育科目)が必修科目だったおかげで、欧米の文化や歴史の中に根付く普遍的な価値観をもって、会話ができ、深い理解に繋がっています。研究テーマを定め直した際にも感じたことですが、2年間リベラルアーツで学んでから留学に来たことが自身の大きな武器になっています。
社会問題等に関する議論が好きな学生が多いところもICUに近いと感じます。日本の鎖国の歴史や、現代の政治体制について質問されたこともありました。最近では、ドイツの近隣国であるウクライナの戦況も頻繁に話題にあがっています。実際にクラスメイトの中にはウクライナからの避難学生がおり、戦争と平和の問題を日々の暮らしの中で考えるようになりました。
国全体として見ると、ドイツは社会全体がICUのように、一人ひとりの個性や思想の違いに寛容です。その背景には、ヨーロッパの地続きの地形や多言語話者が集う環境があると考えています。その分、私のような日本人留学生も特別扱いせず、自然に受け入れてくれています。また、ドイツには大学卒業後に一律で就職する文化がなく、それぞれのキャリア選択を尊重する風潮があります。大学院に進み、修士課程を取得する人も多いそうです。一方、日本では就職活動への影響を懸念して長期留学を断念するケースを耳にします。ドイツのように、卒業後の自由なキャリアパスを歓迎する風潮が日本にもさらに広がることを期待しています。
今後に向けて
留学開始直後は不安があったドイツ語も、半年間でかなり自信がつきました。語学の授業でインプットするだけでなく、放課後や休日にはドイツ人のバディ学生と話し、アウトプットの機会を積極的に設けています。12月にはバディ学生や留学生仲間とクリスマスマーケットに出かけました。ドイツでは11月下旬から12月にかけて、全土がホリデームードに染まります。毎週末マーケットに足を運び、ドイツ文化を堪能しました。
2022年7月から始まった留学も折り返しを迎えました。今後は、アメリカの大学院進学に向けた準備と同時に、卒業研究に取り組んでいきます。大学図書館の資料を参照したり、ドイツ人の先生からフィードバックをもらったりと、現地にいるからこそできる研究を進める予定です。また、帰国までに達成したい目標として、ヨーロッパの国々に訪れ、歴史的建造物やその土地の文化に触れることを計画中。特にナチス・ドイツの歴史を追う上でポーランドにあるアウシュビッツ収容所に足を運ぼうと考えています。帰国後に留学経験を活かした卒業研究を完成させるため、今は存分に視野と経験を広げるつもりです。

(2022年10月取材)